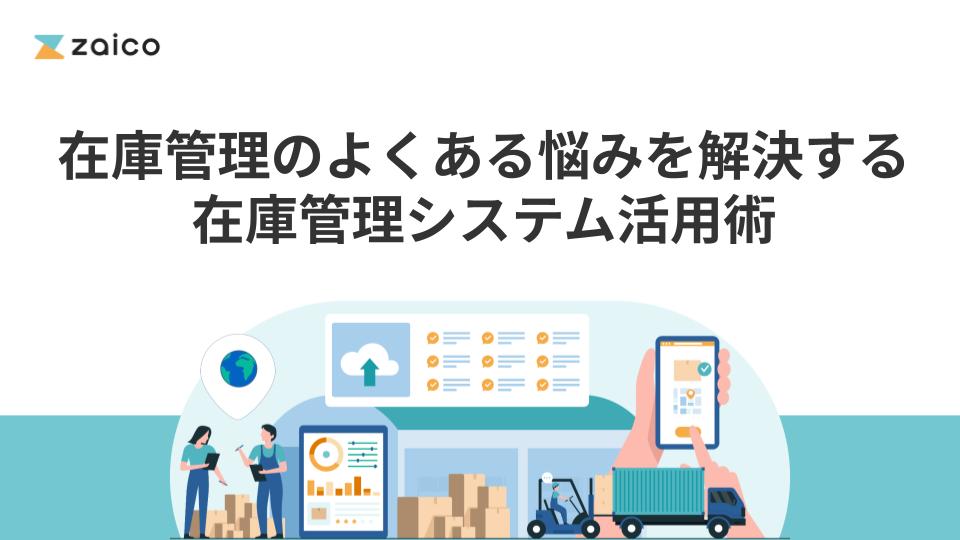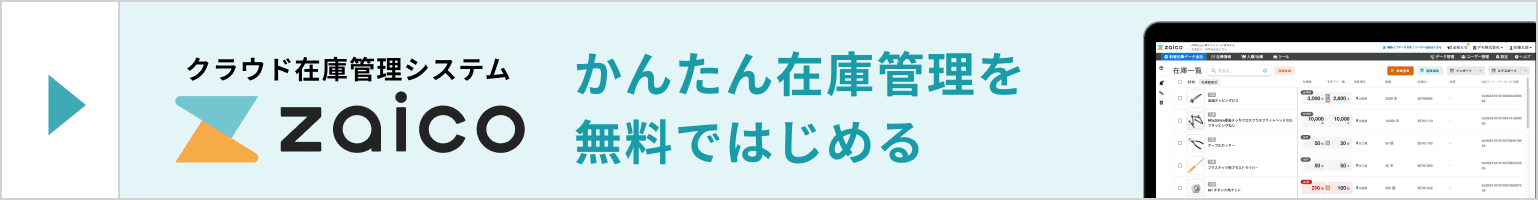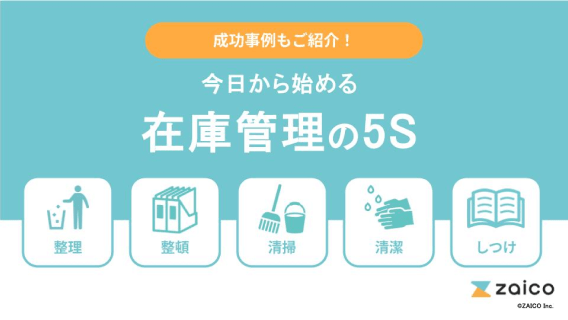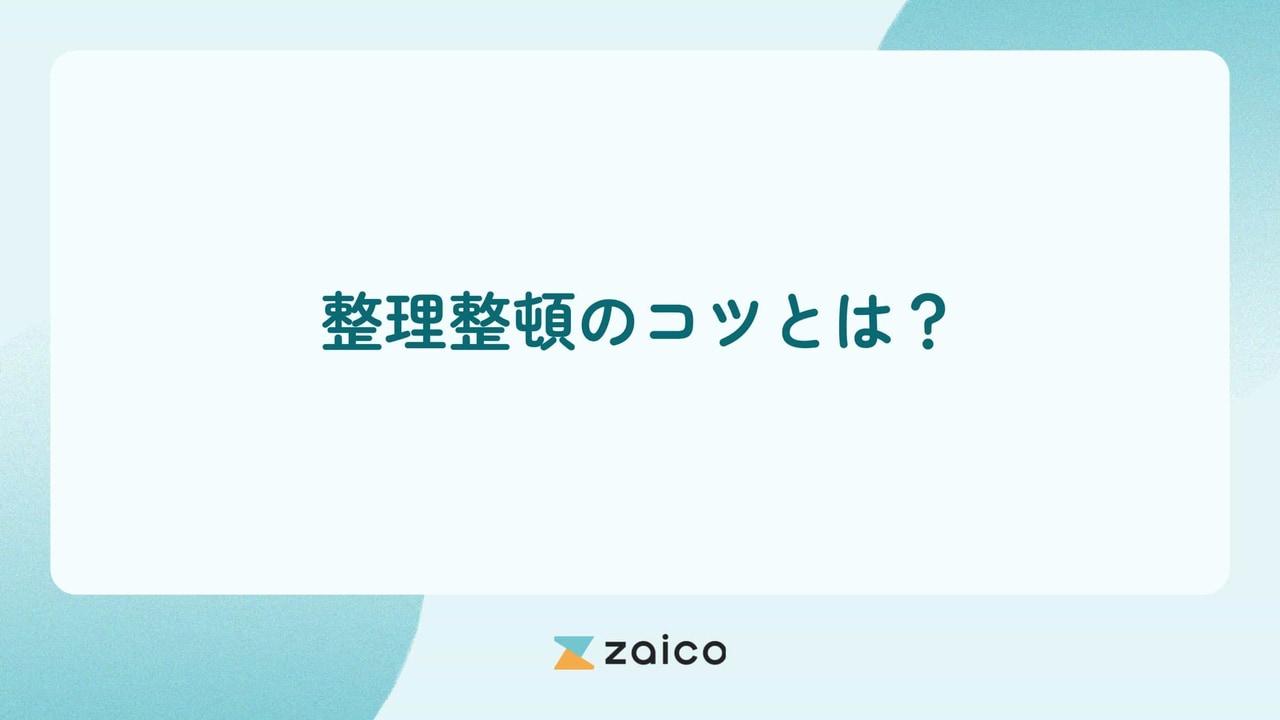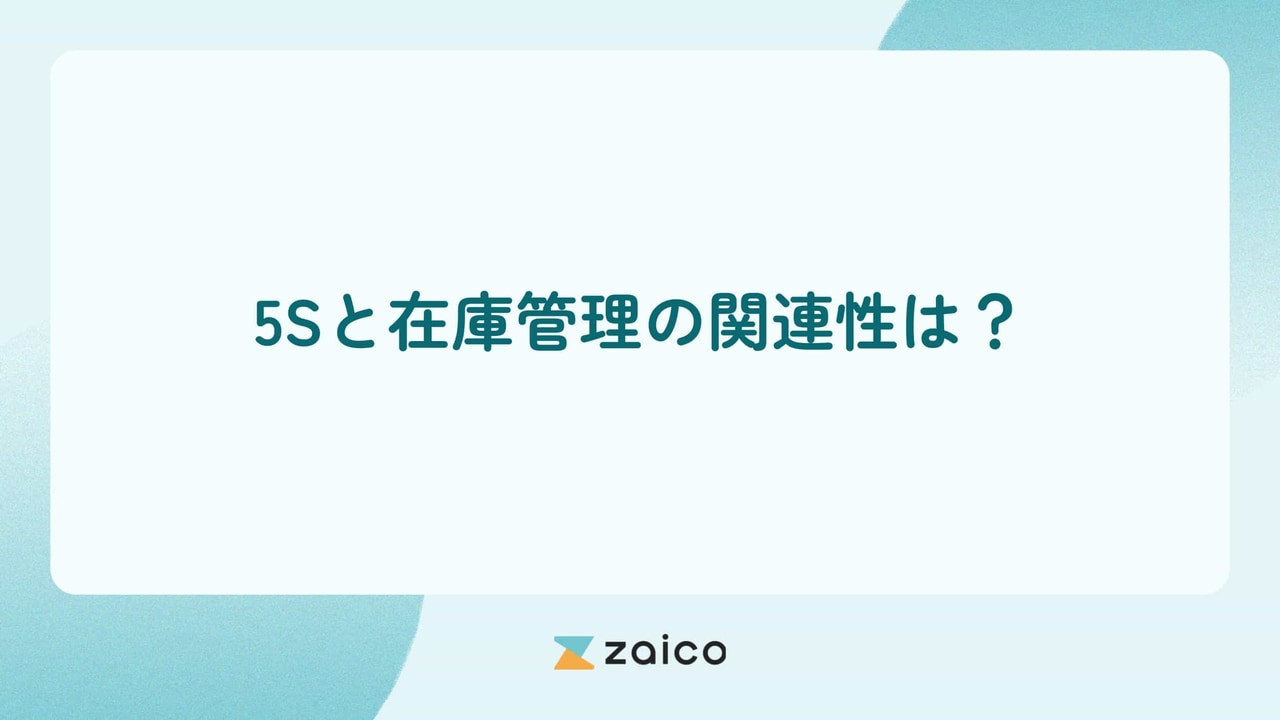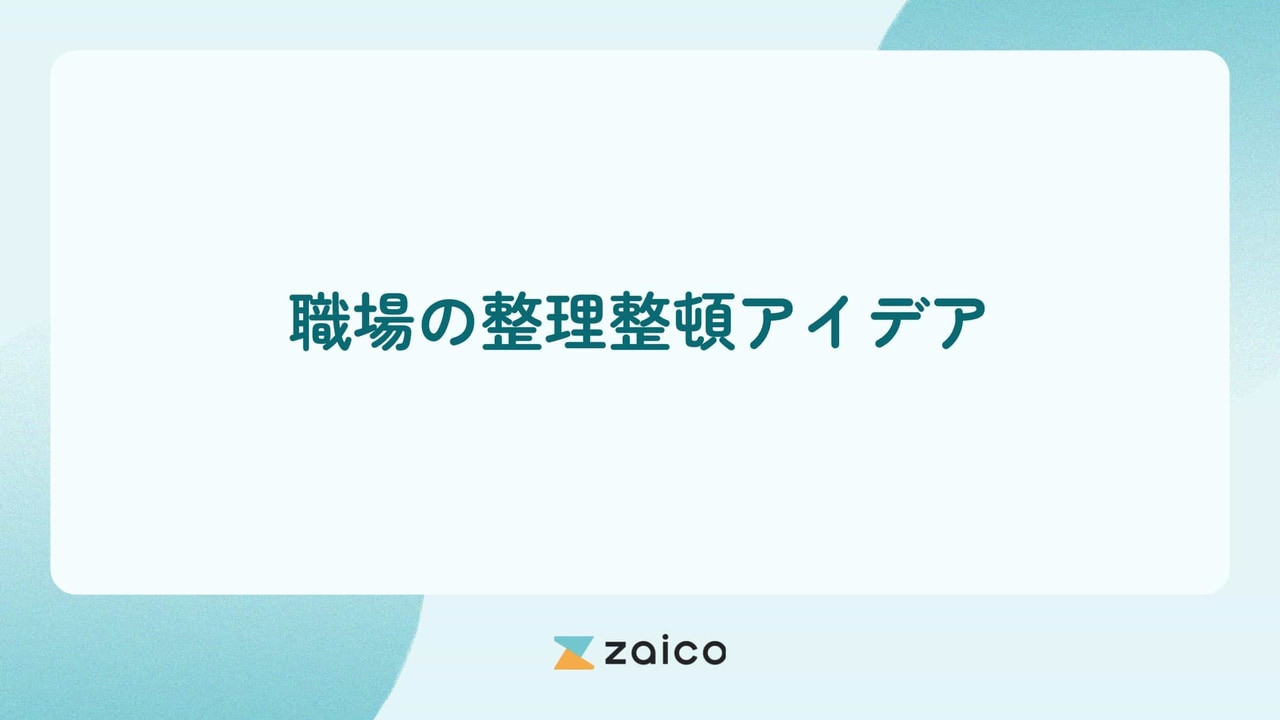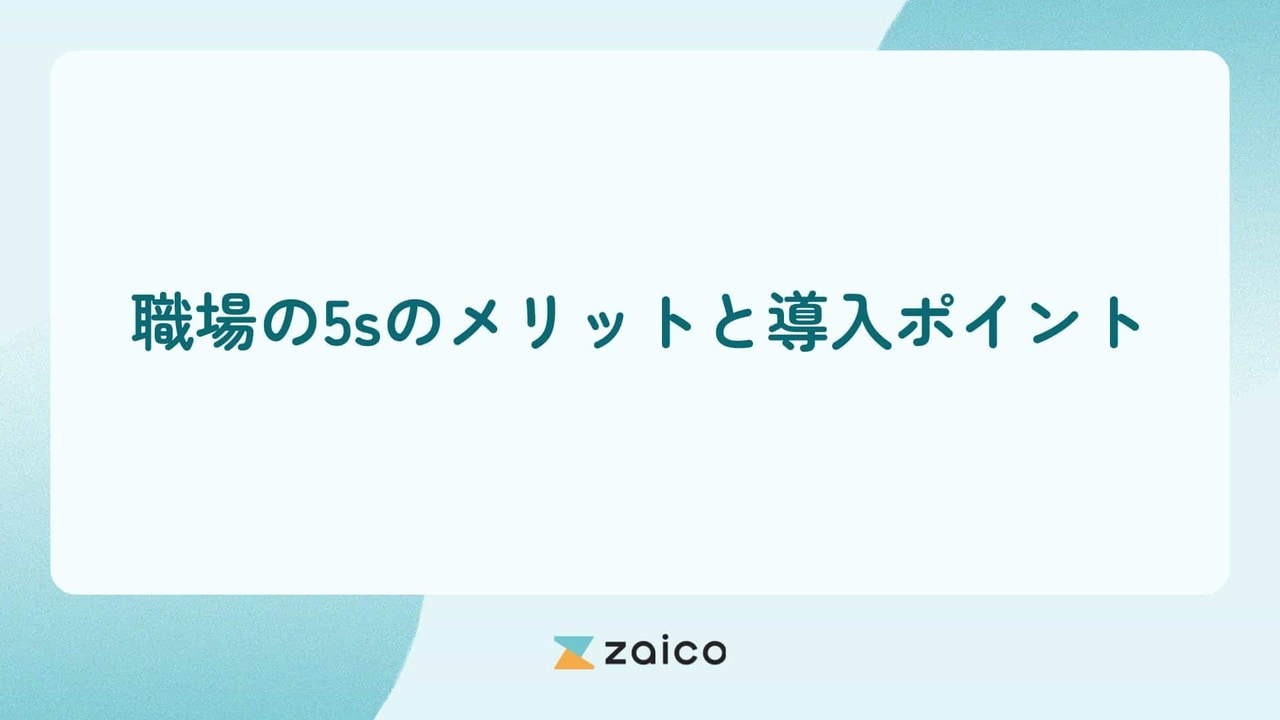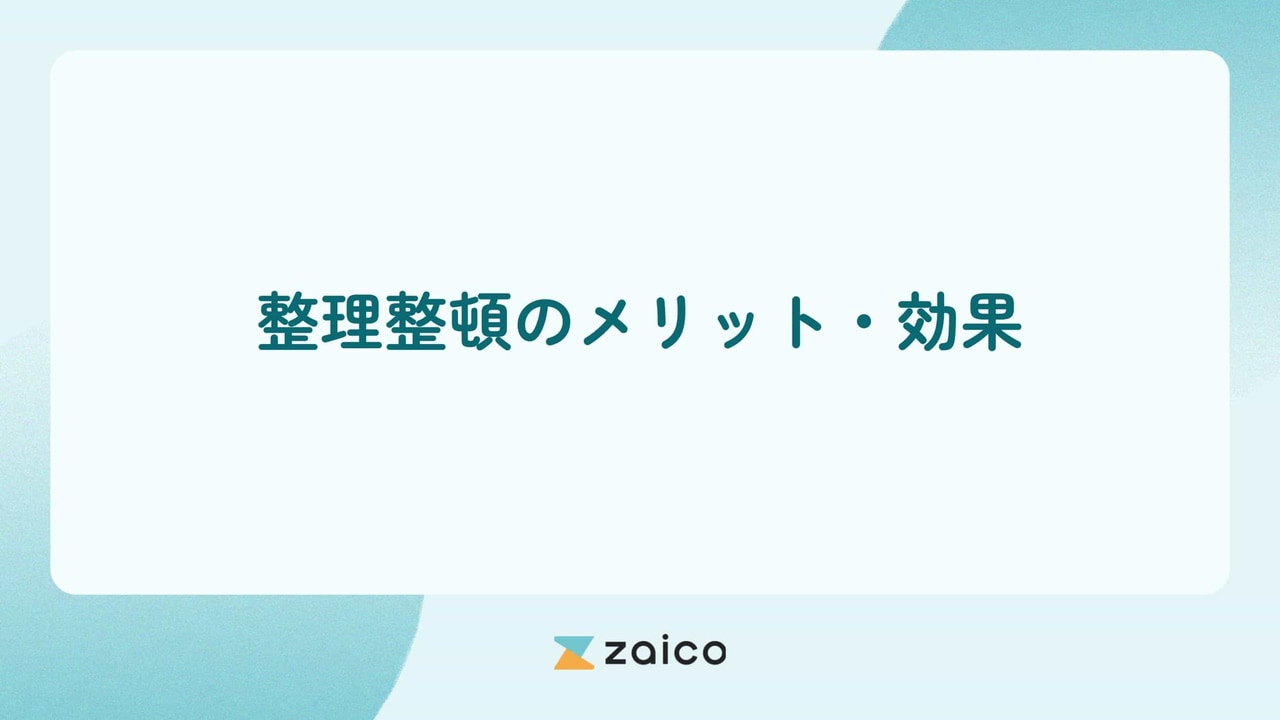商品や物品を扱う際にどこに何があるかわからないというような状況は多くの企業で発生しているものです。
「どこに何があるかわからない状態」は不便なだけではなく作業効率の低下や売上低下、機会損失にも繋がりかねません。
どこに何があるかわからない状態が起きてしまう原因や理由をしっかりと対策する必要があります。
どこに何があるかわからない状態を改善する方法、どこに何があるかわからない状態を放置するリスクについて確認していきましょう。
どこに何があるかわからない状態とは
どこに何があるかわからない状態とは、物品や在庫品などの場所が把握できておらず、必要な時にすぐに見つけられない状況のことを指します。
具体的には以下の状態に当てはまると、どこに何があるかわからない状態になっている可能性が高いといえるでしょう。
- ものを探すのに時間がかかりすぎる
- 倉庫や置き場所が乱雑になっている
- 在庫データと実際の在庫数が一致しない
- 特定の人だけが在庫状態を把握している
- 部署間で情報共有ができていない
小規模な会社から大企業や従業員の規模を問わず、このような状態が起きやすいので、しっかりと改善することが大切です。
また、どこに何があるかわからない状態を放置していると、作業効率低下だけではないさまざまな問題に発展するリスクもあるので、面倒だからと放置するのではなく改善することが求められます。
在庫管理においてどこに何があるかわからないリスク
在庫管理において、どこに何があるかわからない状態を放置するとどのようなリスクがあるのでしょうか。
在庫管理においてどこに何があるかわからない状態になっているリスクについて確認していきましょう。
業務効率を低下させてしまう
在庫がどこに何があるかわからない状態であれば、それを探すための手間がかかるので、業務効率が低下する恐れがあります。
探している間は本来の業務がとまりますし、本格的に探すとなると複数人で探すため、二重の手間となってしまいます。
また、探し物が見つからないという結果になる場合もあり、納期や対応の遅延につながる可能性も高まるでしょう。
従業員のストレスが増える
物が見つからない状況は、業務が止まるだけでなく、棚卸などをしている場合は、従業員のストレスにも繋がってしまうでしょう。
迅速に在庫を用意しなければいけなかったり、棚卸作業を進めているのであれば、焦りや苛立ちが募り精神的負担が増えてしまいます。
また、誰が悪いのかという他責思考が増えたり、「自分のせいではないのか」という自責思考にも陥ってしまうかもしれません。
探す作業が発生してしまう
ものを探すというのは本来の業務ではありません。
そのため、本来の業務以外の業務に時間をかけてしまい、企業全体の生産性低下にもつながるでしょう。
たとえば、探し物のせいで残業時間が伸びてしまったり、本来業務の合間で探す時間を確保しなければいけないという余計な作業が生まれてしまいます。
必要なものが見つけられない
必要なときに必要なものが見つからないと、さまざまな問題が発生してしまいます。
具体的には、以下のような問題です。
- 顧客対応の遅延
- サービスの質の低下
- 棚卸作業の停滞
- 製造ラインの停止
- 企業全体の信頼性の低下
特に顧客との約束が守れないケースは、企業の信頼性そのものに関わる深刻な問題に繋がってしまいます。
在庫数を正しく把握できない
どこに何があるかわからない状態を放置すると、在庫数を正しく把握することができません。
そのため、在庫管理自体が適切にできていないと考えていいかもしれません。
データ上では数が少なくても、実際には在庫があるので在庫過多になってしまっていたり、データ上はあるのに実際にはないという状態かもしれません。
このような状態は在庫管理の不備というだけでなく、販売や使用、棚卸などさまざまな業務に影響を及ぼします。
棚卸に大きな影響を及ぼす
所在不明の在庫品は棚卸作業を複雑化させるため、作業が長引いたり人的コストが増加したりなど、さまざまなトラブルを引き起こしてしまうでしょう。
棚卸は年度末や決算期に行う会社も多いです。
税務関連が遅れると脱税などの問題にも繋がる恐れもあり、会社の信頼がなくなる可能性も考えられます。
欠品が生じやすくなる
どこに何があるかわからない状態は、実質的な欠品状態を指しています。
「あるはず」のものがないので納品ができなくなったり、緊急発注によってコストが増加してしまったりなど、さまざまな問題が生じてしまうでしょう。
特に需要の高い商品の場所がわからない場合、業務が滞ることもあるため、大きな打撃を与えかねません。
過剰在庫が発生しやすくなる
在庫があるはずなのに物が見つからなければ、再発注をしなければいけません。
見つからないだけで在庫がある場合、過剰在庫が発生してしまうので、コストも増加してしまいます。
また、過剰在庫は廃棄ロスの増加など、経営面でも大きな悪影響を及ぼします。
どこに何があるかわからない状態を改善する方法
どこに何があるかわからない状態を改善するには、どうすれば良いのでしょうか。
どこに何があるかわからない状態を改善する方法を確認していきましょう。
使用頻度に合わせて収納場所を用意する
どこに何があるかわからない状態を改善するためには、適した収納場所を作ることが大切です。
たとえば、よく使うものは収納しやすい場所に収納したり、季節によって使う頻度がかわるものは時期に応じて配置を変更してみるといいかもしれません
このように物に応じた収納場所を用意することで、日常的な在庫管理を整理整頓しながら行いやすくなるでしょう。
収納のルールを作る
まずは明確なルールを作ることも大切です。
収納のルールを作成し全員で共有すれば、責任感を抱くことができます。
例えば、以下のようなルールを作成しましょう。
- 収納手順を作成する
- 収納棚にラベルをつけてその通りに収納する
- 例外的に保管しなければならない物ができたときはどこに置くのかを指定する
ルールを作っておけば、ルール通りに収納するだけで済みますが、逆にルールが決まっていないと個人の判断に委ねられてしまうので、乱雑の原因となります。
物の定位置を決めて収納する
基本的に、物は決まった場所に収納しましょう。
棚にラベルをつけたり、定位置に戻せるようにボックスを用意したりなど、収納方法に工夫をつけることも大切です。
あった場所に戻すという当たり前のルールを全員が行えば、どこに何があるかわからない状態を防ぐこともできますし、探す時間を省くこともできます。
物の地図を作る
在庫品の配置図をつくることで、どこに何があるのか把握しやすくなります。
たとえば、棚の区画ごとにどこになにがあるのかリストを作成したり、倉庫全体の平面図を作成すると良いでしょう。
配置場所は視覚的な情報として捉えることができるので記憶に残りやすく、探す手間を省くことができます。
整理整頓を徹底する
基本的なことではありますが、常に整理整頓しておくことが大切です。
どこに何があるのかわからない状態になるのは、日常的に物の出し入れをしながら、違う場所に置いたり配置場所を変えたりしているからです。
そのため、まずは日常的に整理整頓して職場の環境を整えましょう。
ロケーション管理を行う
よりレベルの高い管理方法として、ロケーション管理という方法があります。
ロケーション管理は、保管場所を座標化したり倉庫の区画を細かく分けることで在庫の場所を管理する方法です。
特に多くの在庫品を管理している場合、細かく管理ができるロケーション管理は効果的なので試してみると良いでしょう。
たとえば、バーコードを使ったり位置情報をデータベース化したり、さまざまな方法でロケーション管理は行えます。
持ち出し管理を行う
共用の備品がある場合は、持ち出し管理を徹底させましょう。
たとえば、持ち出し記録の管理簿を作成したり、持ち出した場合の返却期限を設定するなど、さまざま管理方法があります。
持ち出しすることでさらに在庫管理の情報が曖昧になるので、持ち出し備品がある場合は必ず管理方法を徹底することが大切です。
在庫管理システムを利用する
最終的には、在庫管理システムを使うのが効果的です。
在庫管理システムを使えば、リアルタイムで入出庫のデータを記録できますし、在庫移動の記録も簡単になります。
デジタル化することで在庫状態を正確に把握できますし、バーコードやQRコードによる管理ができるので、どこに何があるのかわからないという状態になることを防ぐことができるでしょう。
どこに何があるかわからないの改善にzaico
どこに何があるのかわからない状態は、整理整頓ができていなかったり、乱雑な在庫管理をしていることが原因である可能性は高いでしょう。
どこに何があるかわからない状態を改善したいのであれば、整理整頓などの基本的な改善はもちろん、効率的かつ適切な在庫管理の方法を取り入れる必要があります。
どこに何があるかわからないような在庫管理を改善するために、「クラウド在庫管理システムzaico」の導入をご検討ください。
zaicoは、バーコードやQRコードでの管理もできる在庫管理システムで、紙やエクセルでの管理よりも正確かつ効率的な在庫管理が実現できます。
どこに何があるかわからない乱雑な在庫管理を改善したい場合は、お気軽にzaicoにお問い合わせください。