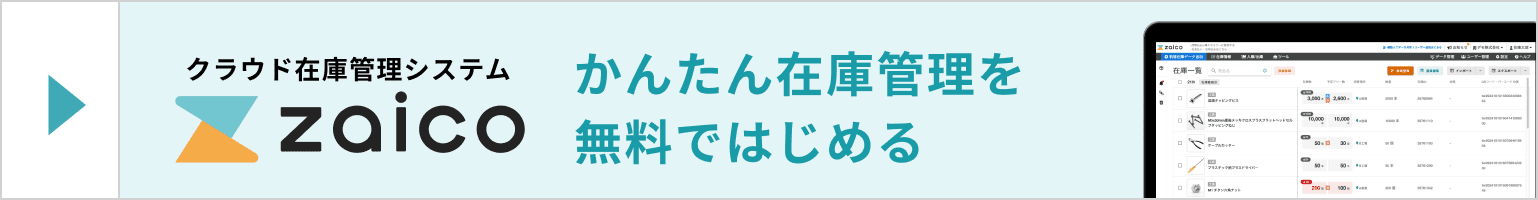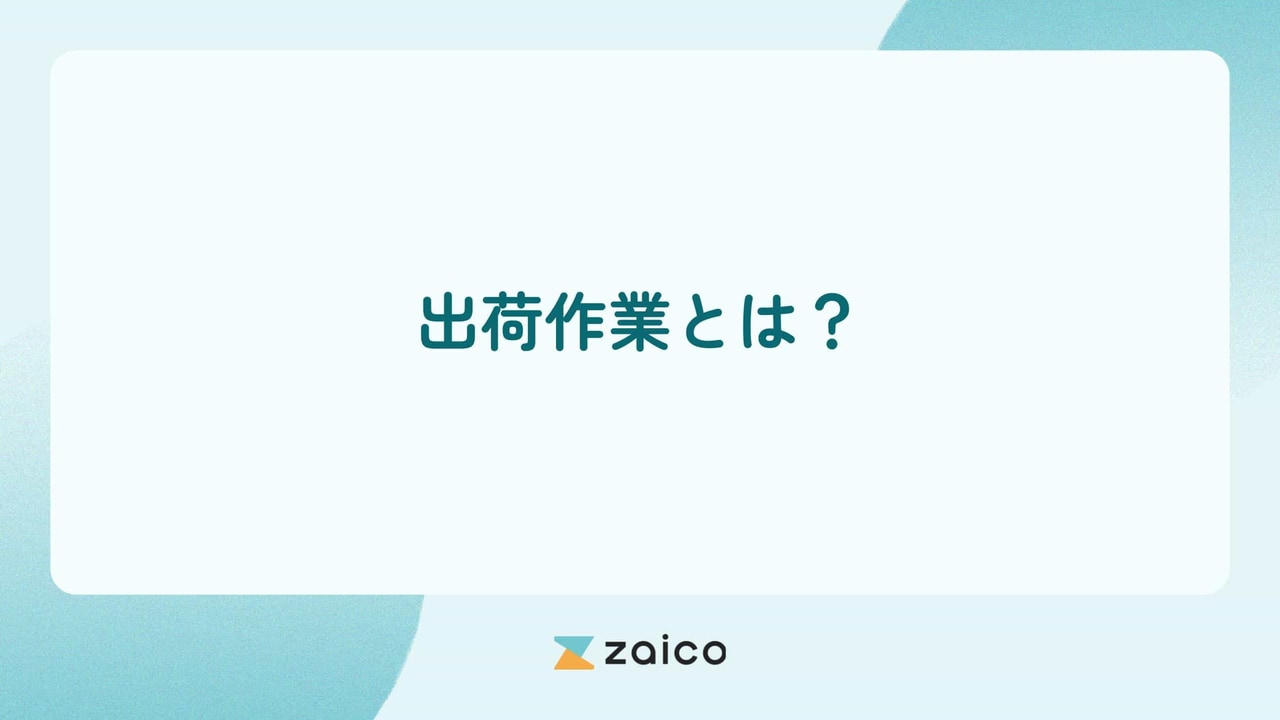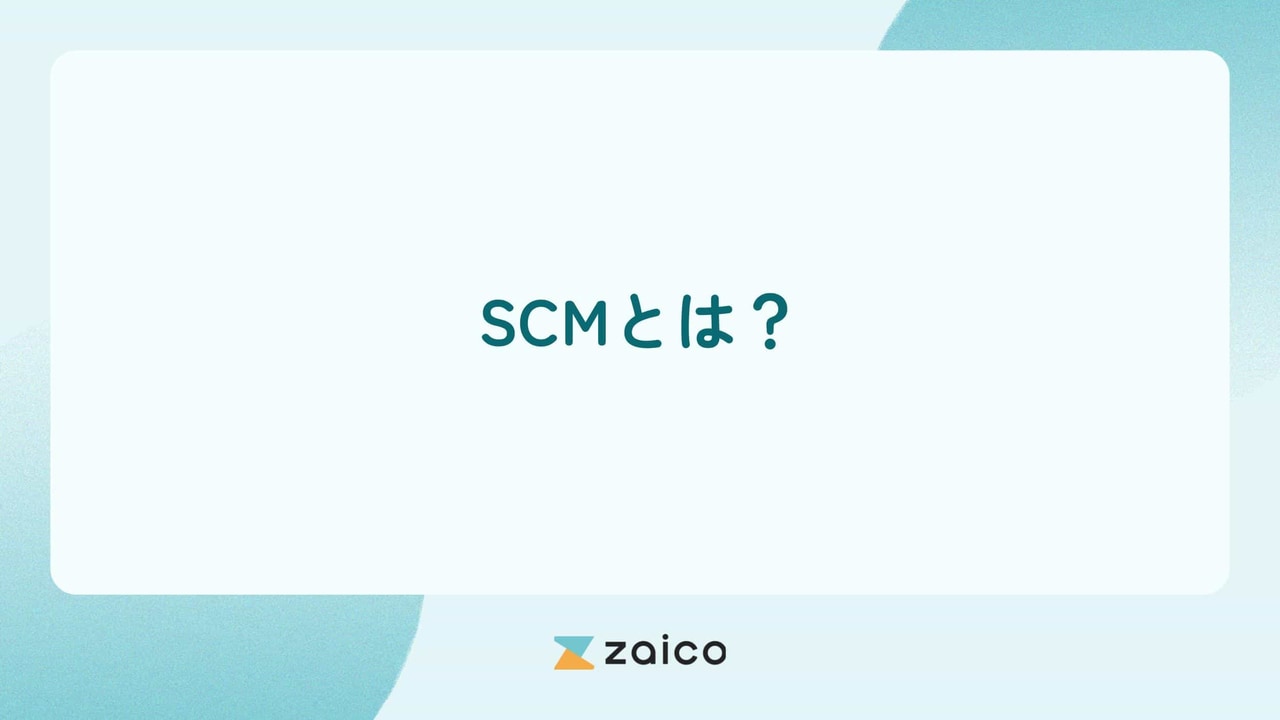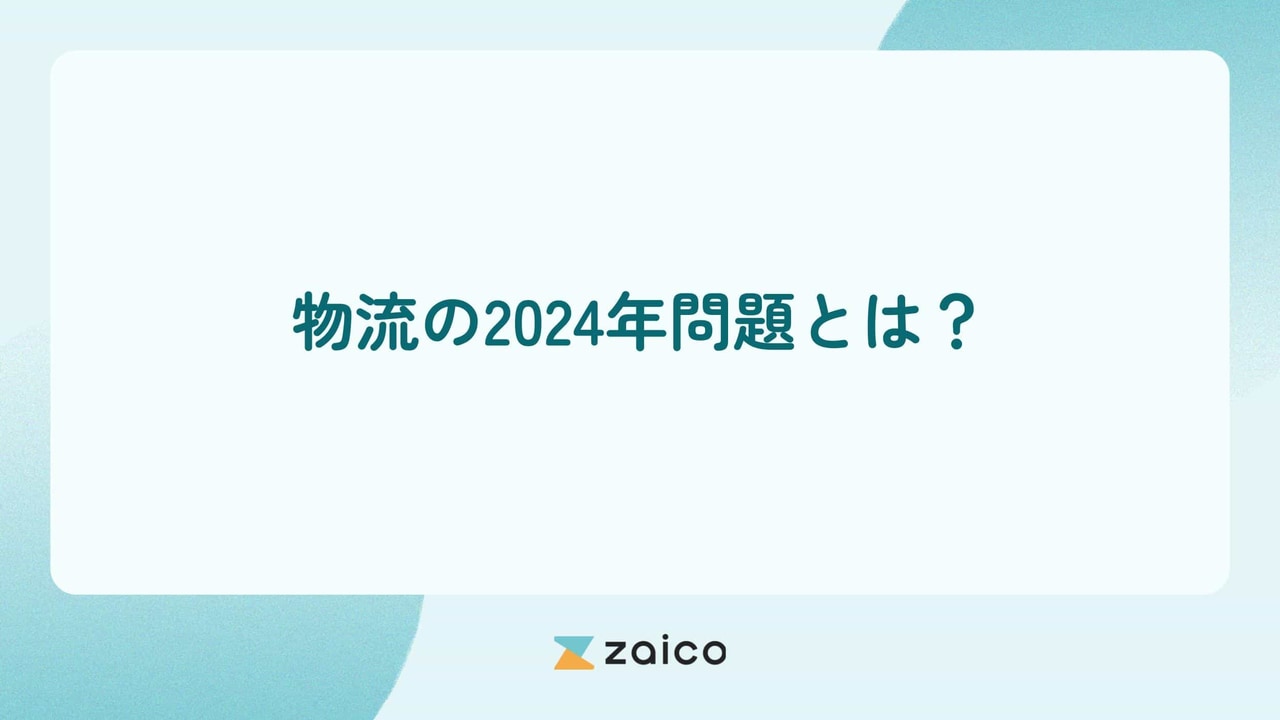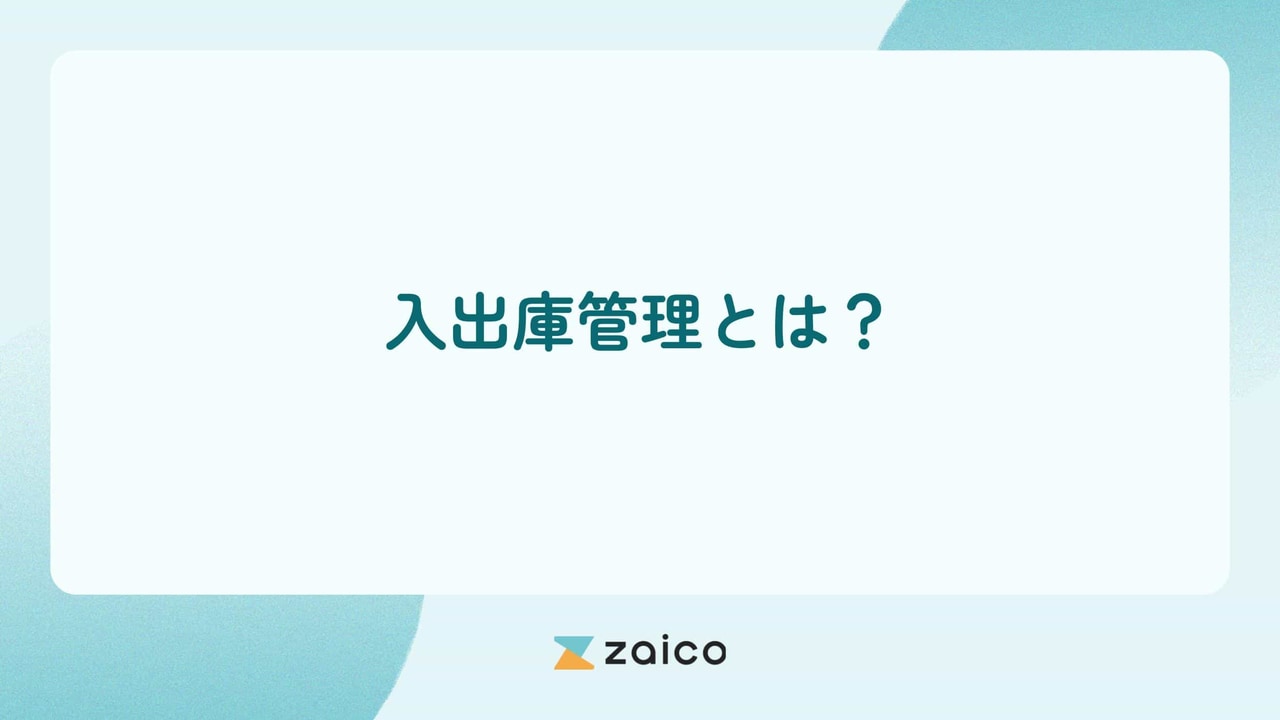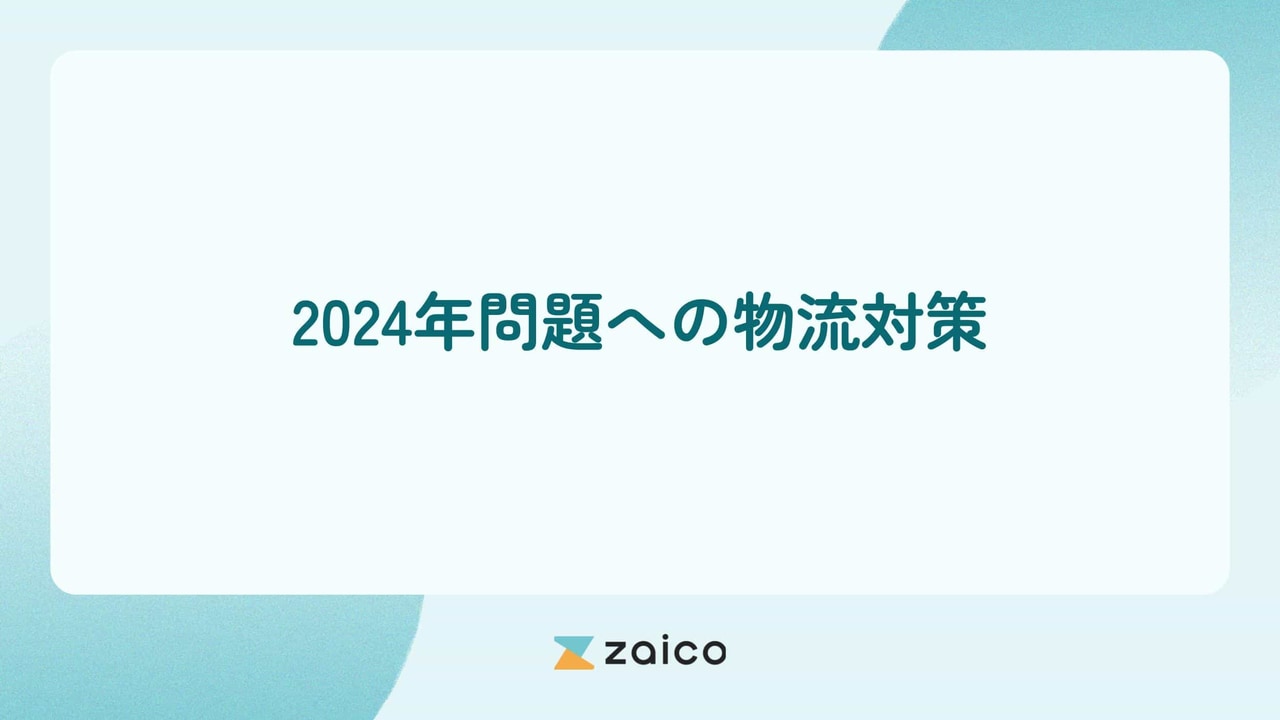1930年代、アメリカのトラック業界で生まれ、発達を遂げた物流システムとして知られる「クロスドック(クロスドッキング)」とはどのようなものなのでしょうか。
耳慣れない響きの「クロスドック」という言葉ですが、時短を図り、コストを低減するための流通戦略として非常に重要な切り札となる配送方法です。
クロスドックとは何か、クロスドックのメリット・デメリットを確認していきましょう。
クロスドック(クロスドッキング)とは?
クロスドック(クロスドッキング)は作業場(ドック)での受け渡しが交差(クロス)するように行われることからこの名がつけられました。
クロスドックは、倉庫を介在させることなく、荷受け先である作業場から、あちこちの配送先である別の作業場へと荷物を仕分けて送り出す配送方式を指します。
倉庫で荷受けして保管している荷物を後から取り出して出荷するのではなく、クロスドックの場合、集荷した商品を開梱したり検品したりせずに荷姿のままその場で仕分けて出荷してしまうので、倉庫管理に関わるコストを抑えることができます。
また、荷物を在庫保管せずに、そのまま次の配送先に出荷する物流センターは「トランスファーセンター(TC)」と呼ばれ、クロスドックはトランスファーセンターで実施される配送方法といえるでしょう。
クロスドックのメリット
クロスドックのメリットは、在庫を持たないため商品の保管料やピッキングなどの倉庫関連業務に対するコストがかからない点が挙げられます。
また、クロスドックは在庫を持たず必要な分だけを仕入れて納品するので、売れ残りの在庫をかかえずにすむ、保管スペースを必要としない、という点も大きなメリットでしょう。
こうした点からクロスドックは、下記事業者により適合した配送方法と言えるでしょう。
- 取扱う商品の品目数は多いが、一度に納品する数量はそれほど多くないという事業者
- 大規模な施設や大勢のスタッフを抱えたくないと考える事業者
「売れる分だけ揃えて売りたい」、「在庫を抱えることで発生する費用はできる限り抑えたい」というニーズに合致しているのがクロスドックです。
クロスドックのデメリット
クロスドックのデメリットは取り扱う商品の数量が基本的に小ロットになる点が挙げられます。
そうなると大量入荷によって単価が安くなるボリュームディスカウントを受けられないので、仕入れ単価はどうしても高くなる傾向にあります。
また、クロスドックでは、倉庫という拠点がありませんので、仕入れ先からの荷物を受け入れ、配送するための場所・日時を設定し調整する作業がより煩雑化します。
取り扱う商品が増えれば増えるほど管理者の負担が増します。
さらに、日時調整に失敗すると余分な保管料や人件費が発生するリスクが生じてきます。
クロスドックは高い情報管理能力、現場指揮能力などが必要となる配送方式であることは覚えておくべきでしょう。
クロスドックが可能な物流センターとは?
クロスドックを得意とするのがトランスファーセンター(TC)と呼ばれる物流センターです。
TCのほかにも物流センターにはDCやPDCといった種類があります。
クロスドックが可能な物流センターであるTCやDC、PDCといった物流センターの種類を確認していきましょう。
TC(トランスファーセンター)
トランスファー(Transfer)は「移送」「転送」という意味です。
トランスファーセンター(TC)は基本的に荷物を在庫保管せず、入荷・検品・仕分けを行い、配送先へと送ることを主業務とする物流センターのことを言います。
TCは「通過型物流センター」とも呼ばれ、クロスドックの委託先として最適な物流センターであり、TCでは多くの企業のクロスドックの受け入れを行っています。
TCでクロスドックを行う場合、商品がTCに届いたら開梱や検品作業を行わず、荷姿のままトラックに積み込んで、配送先へと運搬します。
スーパー、コンビニ、大型量販店などはTCを利用することが多く、小ロット多頻度の配送ニーズに迅速な対応をします。
DC(ディストリビューションセンター)
ディストリビューションセンター(DC)は在庫を持つ物流センターです。
そのため、DCは「在庫型物流センター」とも呼ばれ、商品を保管し、注文に応じて検品・ピッキング・梱包を行い出荷する機能を持っています。
TCが商品を荷姿のまま積み替えるのを主業務とするのに対し、DCは注文から納品までの工程においてより深く商品に関与する機能を持つ物流センターだと言えます。
クロスドックだけでなく、注文を受けてから出荷までの代行業務に対応してほしいという業者はDCの活用がお勧めです。
その一方で、在庫管理費や発送代行のための費用が必要となるので、TCに比べるとかかるコストは当然高くなります。
PDC(プロセスディストリビューションセンター)
DCの機能をさらに高度化させた物流センターとして位置づけられるのがプロセスディストリビューションセンター(PDC)です。
PDCは部品の組み立て、鮮魚・精肉の加工など、物流センターでありながら工場のような機能を持っています。
商品を提供する側にとって、商品の差別化を図ることは重要な販売戦略になります。
「商品にギフトラッピングをして高級感を出したい」、「食品の鮮度を保つために冷凍保存をしてほしい」などの利用者ニーズに応えるための物流センターがPDCであると言えるでしょう。
一方、PDCは高度化、専門化された物流センターであるだけに利用した場合のコストはどうしても高くなるというデメリットもあります。
クロスドック以外の物流効率化の仕組み
クロスドックは商品を荷姿のまま配送することで在庫管理に関わるコストを抑え、物流の効率化を図れます。
クロスドック以外で物流の効率化を図るための有効な手段にはどのようなものがあるでしょうか。
クロスドック以外で物流の効率化手段である「ミルクラン」と「コンテナラウンドユース」について確認していきましょう。
ミルクラン
牛乳メーカーでは牧場を巡回して原料である生乳を集荷します。
このことに因み、製造販売業者が原料供給業者を巡回して目的の原料や品物を集荷していく方法を「ミルクラン」あるいは「巡回集荷」と呼びます。
商品を売る側で車両を出し、原料や資材を扱う業者を巡回し、これらを調達することで、複数の原料供給業者から請求される搬送費を発生させません。
また、必要な分だけ都度仕入れることになるので原材料の余剰が出にくくなります。
ミルクラン方式は、近隣に原材料を取り扱う業者が集まっている場合においてコスト削減の有効な手段といえます。
コンテナラウンドユース
コンテナラウンドユース(CRU)とは、輸入するときに使ったコンテナを荷卸して空になったコンテナを港に停泊する船に戻さずに、中継地点で別のトラックに取り付けて輸出用の荷物を集荷するためのコンテナとして使い、集荷した状態のコンテナを船に戻し空送する方法のことを言います。
CRUにより空になったコンテナを船舶に戻す工程を省くことで、輸送コストの削減、CO2の削減、港湾渋滞の解消、ドライバーの作業効率改善などを推し進めていくことが期待されています。
こうした点から近年において、国土交通省や経済産業省、地方自治体などがCRUの法整備や助成事業などを推進して、その普及を図っており、CRUは物流業界で注目が集まっている運輸システムとなっています。
クロスドックやクロスドック以外の在庫管理にzaico
クロスドックは在庫を抱えず、荷物を荷姿の状態であちこちの配送場へと送っていく方法になり、在庫管理に要するコストを抑えられます。
しかし、クロスドックの場合、倉庫という拠点を介さずに商品の受け渡しが行われるので、仕入れから配送までの場所・日時などの管理・調整作業が煩雑化し担当者の負担は大きくなりやすく、とくに商品の入出庫管理は非常に重要な業務となります。
商品の入出庫管理の課題を抱えていたり、改善したいとお考えであれば「クラウド在庫管理システムzaico」の導入をご検討ください。
zaicoは写真やバーコードの情報をハンドスキャナーで取り込み、品物を登録します。
これにより帳簿への手書きミスを防いだり、PCへの入力業務などの手間を省けるので、在庫管理の効率化を実現できます。
また、これらの登録情報をもとに入出荷の管理、倉庫の保管を円滑に進めていく機能も搭載されています。
さらに、登録情報はQRコードやスマホで追跡することが可能となっており、データは複数人で同時に閲覧できるため、スタッフ各自が所有するパソコン、スマホ、タブレットなどで在庫情報の管理と共有が行えます。
商品や倉庫の在庫管理に在庫管理システムの導入をご検討の場合、お気軽にzaicoにお問い合わせください。