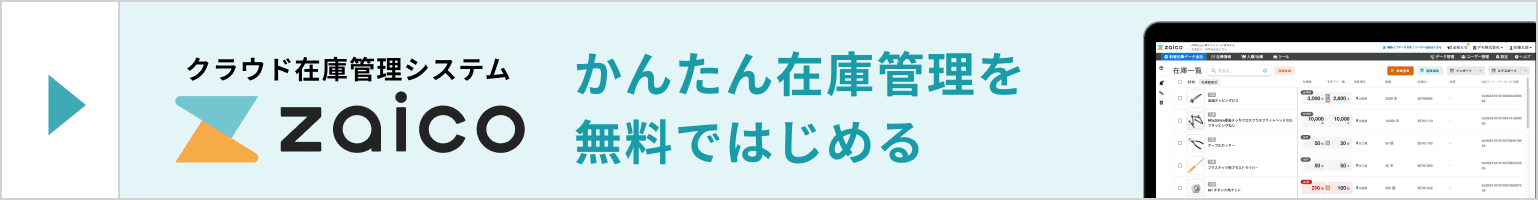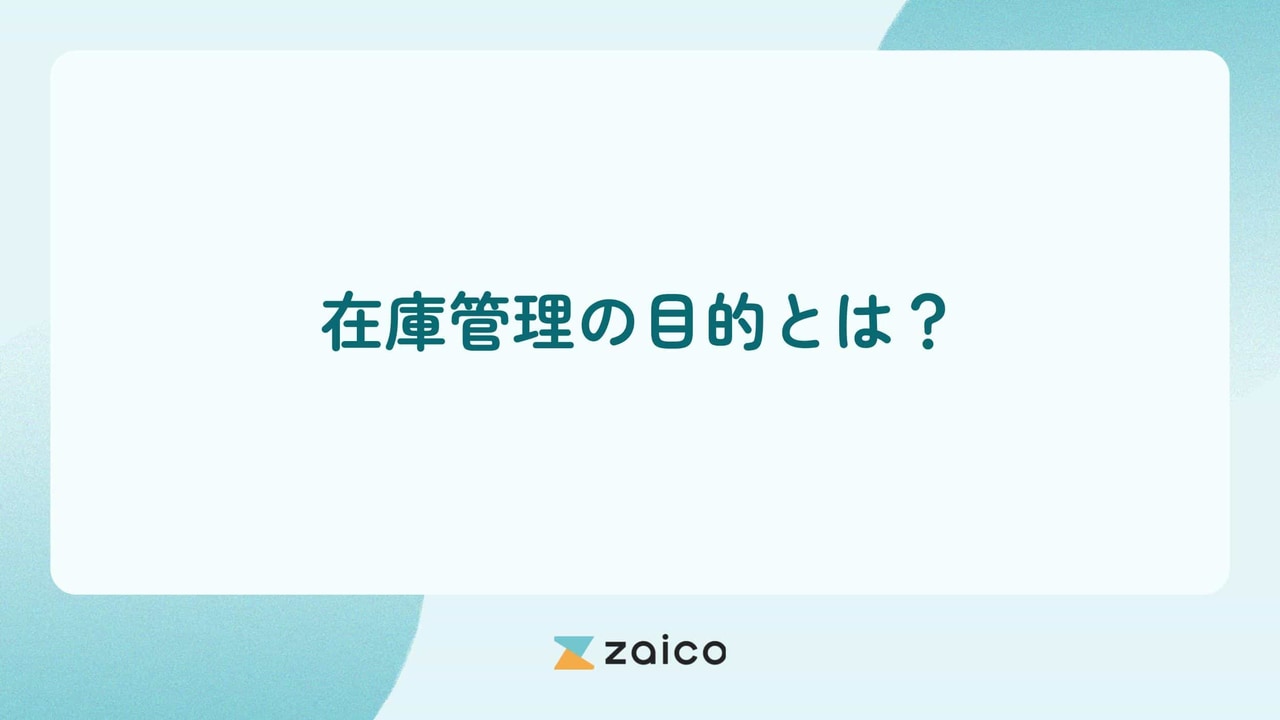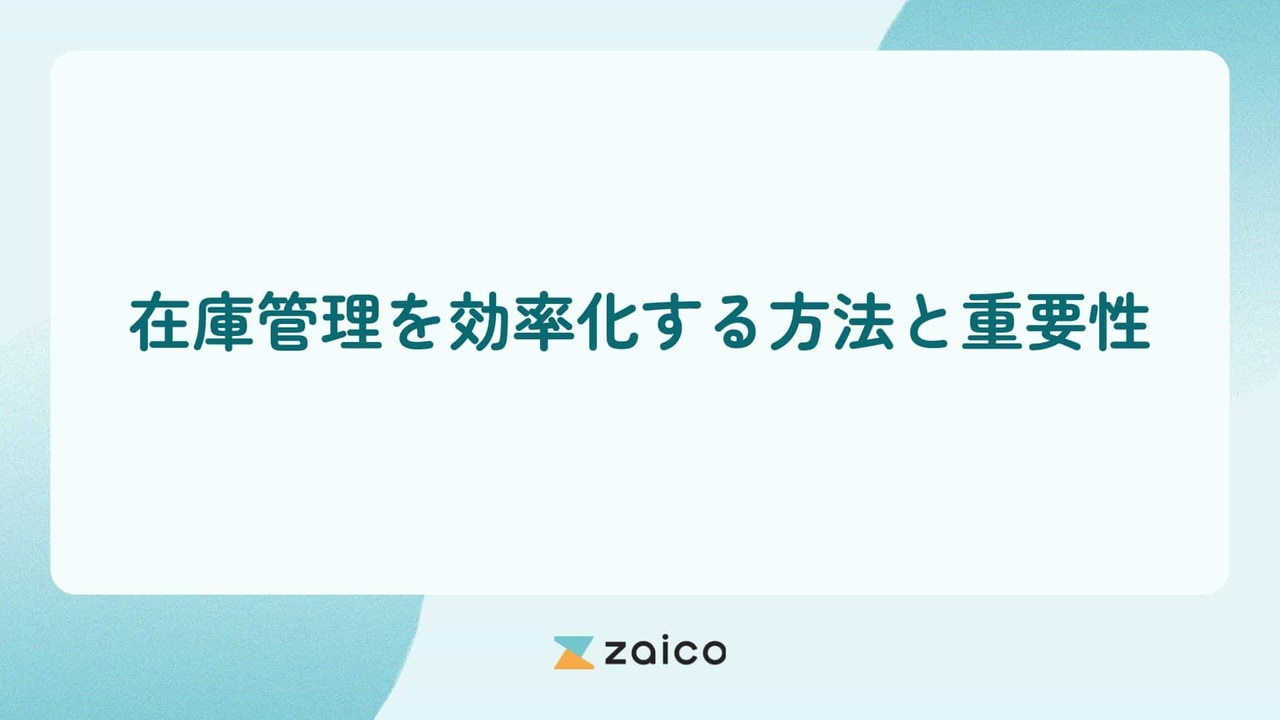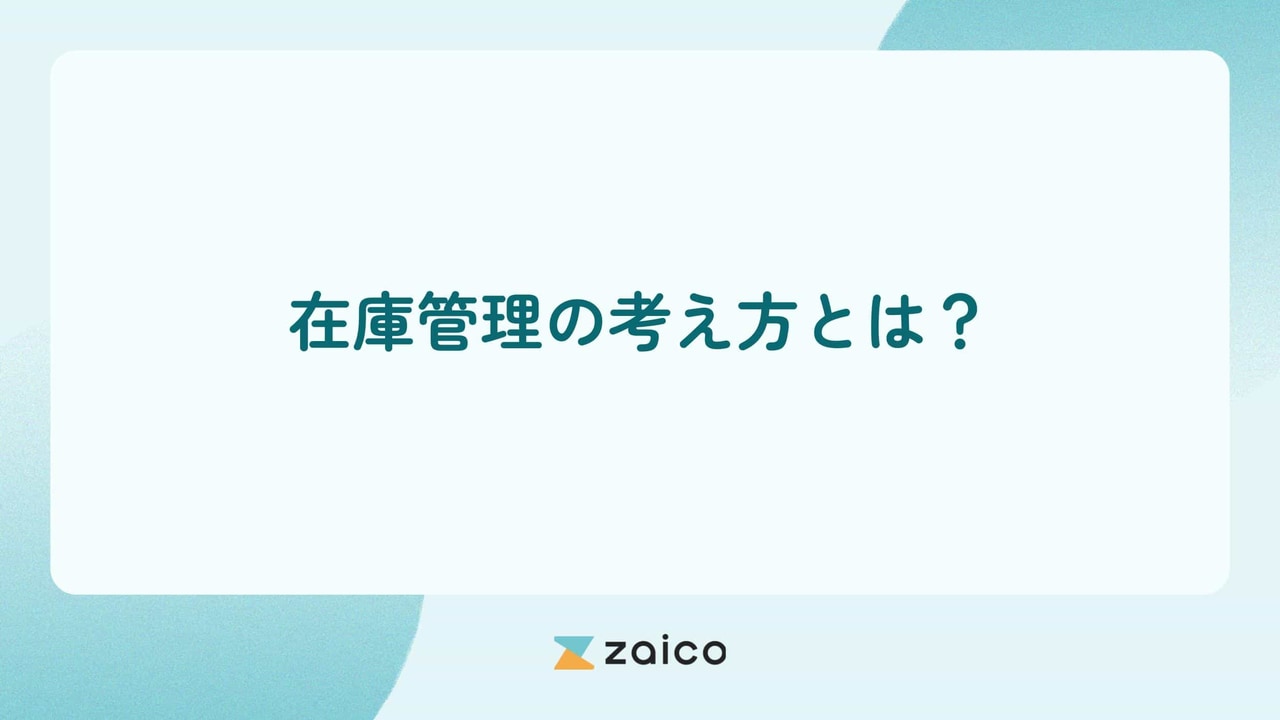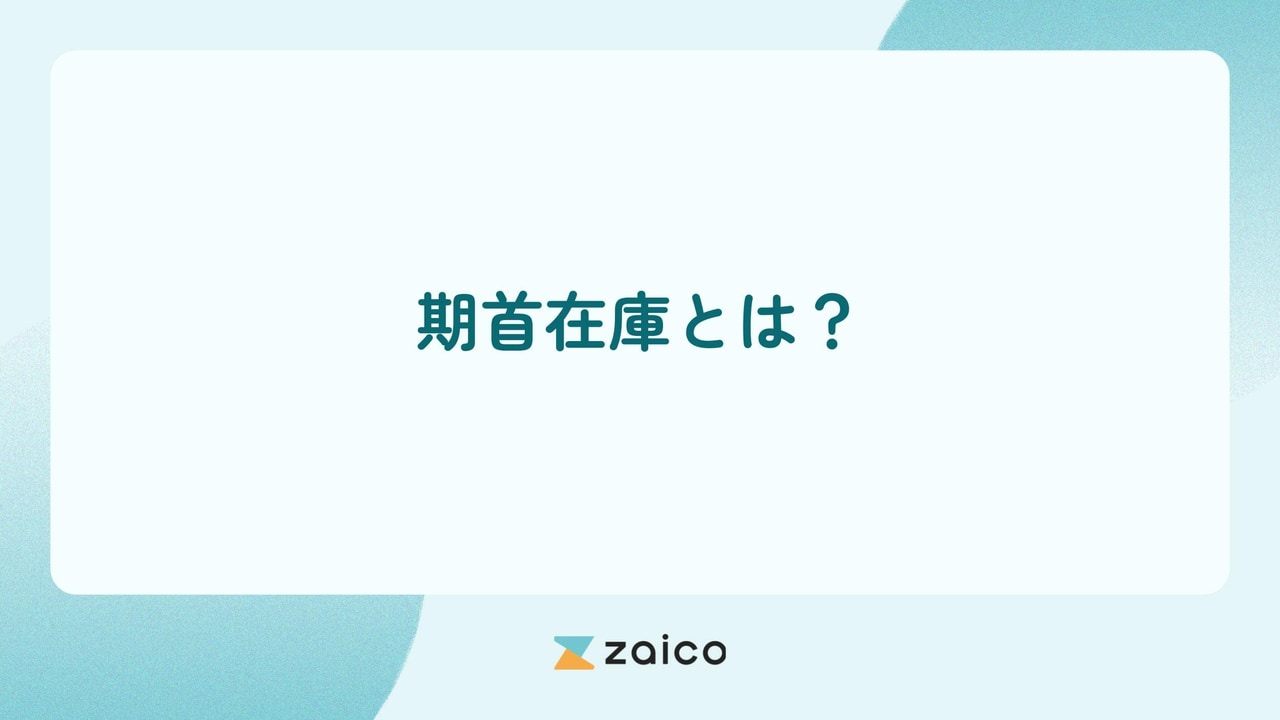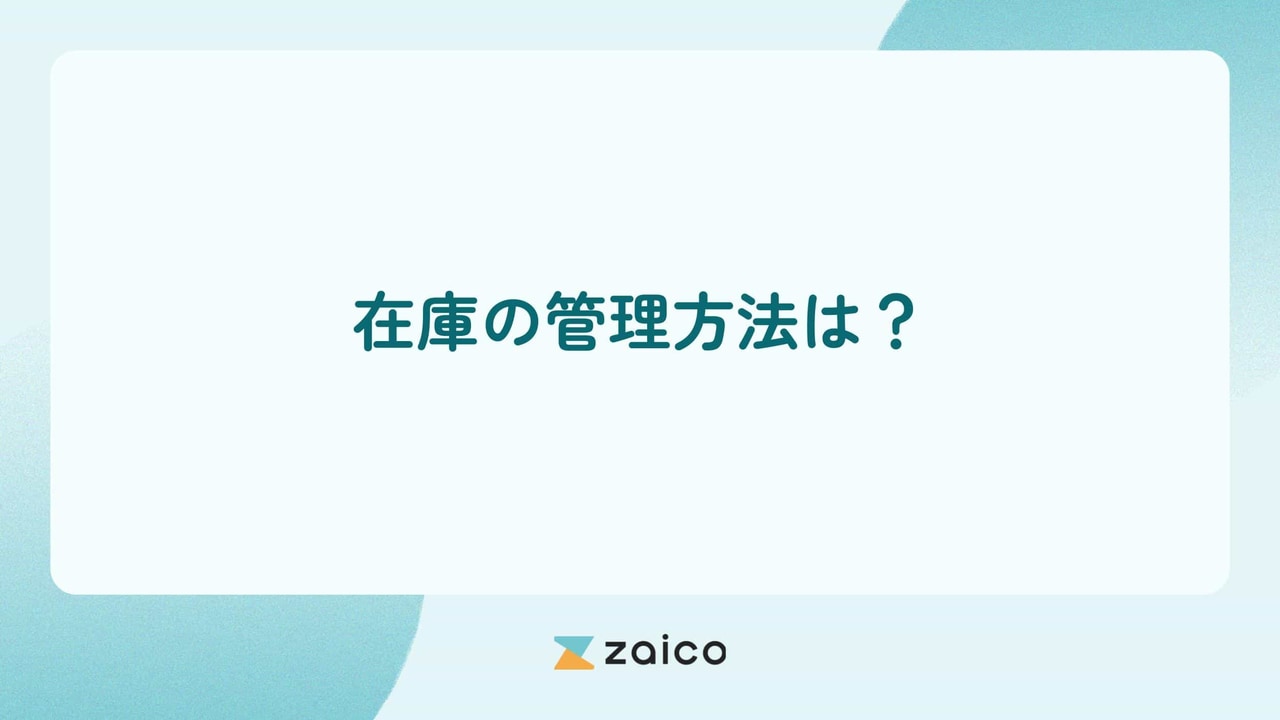在庫管理の現場で、「商品が見つからない」「数が合わない」というトラブルは良く怒ってしまうものです。
在庫管理のトラブルを防ぐカギが「現品管理」にあります。
現品管理は、在庫情報を正確に把握し、効率的な運用を実現するための土台となるプロセスです。
現品管理とは何かから、現品管理と在庫管理の違い、現品管理のメリットや流れを確認していきましょう。
現品管理とは
現品管理とは、企業が所有する原材料や仕掛品、製品などの在庫の「現品」について、実際の数量や状態を正確に把握し、適切に管理する業務のことです。
「現品」とは、在庫管理における実物のことを意味し、帳簿やシステム上のデータと対比される実在物を指します。
現品管理では、商品がどこに、どのような状態で保管されているかを確認するため、定期的な棚卸しや保管場所の記録、品質のチェックなどを行います。
製造業や小売業において、現品管理は、原材料や商品の紛失・破損を防ぎ、適正な在庫水準を維持するために不可欠な管理活動です。
現品管理と在庫管理の違い
現品管理と混同しやすい言葉に、在庫管理があります。
両者の違いを簡単に言うと、現品管理は在庫管理の一部であり、在庫管理の土台となるものです。
現品管理は、物そのもの(現物)を管理することに焦点を当てています。
一方、在庫管理は、現品管理を含む、在庫に関するより広範囲な管理活動を指します。
現品管理ができていないと、在庫管理は成り立ちません。
現品管理がずさんで、どこに何がいくつあるのか正確に把握できていない状態では、適切な在庫水準の維持も、正確な棚卸も困難です。
例えるなら、現品管理は「家の整理整頓」、在庫管理は「家計の管理」といえるでしょう。
家の中が整理整頓されていなければ、何がどこにあるのか分からず、無駄なものを買ってしまったり、必要なときに必要なものが見つからなかったりします。
これは、現品管理ができていないために、在庫管理(家計の管理)がうまくいかない状態といえ、現品管理は在庫管理の基盤であり、両者は密接な関係にあります。
現品管理を徹底することで、在庫管理の精度を高め、企業の経営効率向上につなげることが重要です。
現品管理を適切に行うメリット
在庫管理の効果を高めるうえで、適切な現品管理は欠かせません。
現品管理を適切に行うメリットを確認していきましょう。
コスト削減につながる
現品管理を適切に行うことで、在庫の過不足を防ぎ、無駄な仕入れや余剰在庫の保管コストを削減できます。
例えば、現物の数量や状態を正確に把握することで、不要な発注を避けることが可能です。
現品管理が不十分だと、過剰在庫による保管スペースの圧迫や廃棄コストが発生し、企業収益を圧迫しかねません。
適切な現品管理によって、在庫コストを最適化し、企業の収益に貢献します。
品質維持につながる
現品管理は、製品の品質を維持する上でも重要な役割を果たします。
適切な保管場所や保管方法、温湿度管理などを行うことで、製品の劣化を防ぎ、品質の維持が可能です。
不適切な管理では劣化した商品が納品されるリスクが高まり、顧客満足度にも悪影響を及ぼしかねません。
適切な現品管理は、製品の信頼性向上と顧客からの評価向上につながります。
紛失・破損リスクが低減される
現品管理を徹底することで、在庫品の紛失や破損リスクの低減も可能です。
現品管理が適切でない場合、在庫品の所在が不明瞭になり、紛失や盗難のリスクが高まります。
また、不適切な保管方法によって、製品が破損する可能性もあるでしょう。
適切な現品管理によって、紛失・破損リスクを低減し、大切な資産である在庫を守れます。
作業効率の向上が期待できる
現品管理の徹底により、作業効率が向上します。
例えば、商品の保管場所や状態が明確であれば、必要な商品を迅速に取り出せるため、ピッキングや出荷作業の時間短縮が可能です。
現品管理が適切でない場合、必要な物を探すのに時間がかかったり、人的ミスが発生したりするリスクが高まります。
適切な現品管理により、現場全体の作業効率を高め、より迅速で正確な対応が可能です。
現品管理の流れ
現品管理を適切に行うためには、一連の作業を効果的に実施することが重要です。
現品管理の基本的な流れを確認していきましょう。
物品の受け入れ
物品の受け入れは、現品管理の最初のステップです。
納品書と現物を照合し、品名や数量、状態などを確認します。
異常があれば、納入業者に連絡し、適切な対応が必要です。
受け入れ時の記録は、後の工程で重要な情報となるため、正確な作業が求められます。
保管場所への仕分けとロケーション登録
受け入れた物品は、保管場所へ仕分けられ、ロケーション登録が行われます。
ロケーション登録とは、物品の保管場所(棚番地など)を記録することです。
ロケーション登録により、物品の所在を明確にし、必要なときに迅速に取り出せます。
仕分けの際には、物品の種類、特性、保管条件などを考慮し、適切な場所に保管することが重要です。
物品の適切な保管
仕分け・ロケーション登録された物品は、適切な方法で保管されます。
保管には、温度や湿度、保管場所、保管容器など、さまざまな要素の考慮が必要です。
物品の特性に合わせた適切な保管方法の選択が、品質劣化を防ぎます。
保管状況は定期的に点検し、異常があれば適切に対応することが重要です。
棚卸作業による定期的な確認
定期的な棚卸を実施し、帳簿やシステム上の在庫数と現物の数を照合します。
棚卸により、在庫不足や過剰在庫、紛失、状態劣化などの早期発見が可能です。
差異や問題が発見された場合は、原因を調査し、必要な修正を行います。
棚卸の頻度は、業種や商品特性に応じて適切に設定することが重要です。
現品管理の手法
現品管理には、企業規模や取扱商品の特性に応じて、さまざまな手法が存在します。
それぞれの手法にはメリットとデメリットがあり、自社に最適な方法を選択することが重要です。
代表的な現品管理の手法を確認していきましょう。
手作業による現品管理
手作業による現品管理は、紙やエクセルを用いて物品の情報を記録・管理する方法です。
物品の入出庫、棚卸などを手作業で行い、その結果を紙やエクセルに記録します。
初期コストがほとんどかからず、中小企業や小規模な店舗などでも導入しやすい手法です。
一方で、ヒューマンエラーが発生しやすく、入力ミスや記録漏れによる在庫ずれが起こりやすいため、大規模な物品の管理には不向きでしょう。
管理対象が多くなり、手作業での管理に無理が出てきたら、次のシステム導入がおすすめです。
在庫管理システムとバーコードやQRコードによる現品管理
在庫管理システムとバーコードやQRコードを組み合わせた現品管理は、専用のスキャナーやスマートフォンなどを使って物品の情報を自動で記録・管理する方法です。
正確性と効率性に優れており、入力ミスを大幅に削減できます。
また、在庫状況を即座に把握できるため、欠品や過剰在庫のリスクを低減させることも可能です。
ただし、導入には一定のコストがかかります。
しかし、中規模以上の現品管理では、長期的に人件費削減やミス防止によるコスト効果が期待できるでしょう。
IoTを活用した現品管理
IoTによる現品管理では、センサーやRFIDタグを使用して在庫情報を自動収集・分析する方法です。
リアルタイムで正確な在庫データを取得できるため、大規模倉庫や物流センターなどで高い効果を発揮します。
また、人為的な作業が減少し、大幅な効率化が期待できます。
ただし、導入コストが高く、システム構築には専門的な知識が必要です。
物流業や製造業、大規模倉庫を運営する企業などに適しているでしょう。
現品管理の効率化にzaico
現品管理とは、企業が持っている在庫の「現品」について、実際の数量や状態を正確に把握し、適切に管理する業務のことです。
現品管理は在庫管理の一部であり、在庫管理の土台となります。
現品管理を適切に行うことで、コスト削減や品質維持、作業効率向上などの効果が期待できるでしょう。
現品管理には、手作業のほか在庫管理システムやIoTなどのデジタル技術を活用した方法があります。
在庫管理システムを使った現品管理の効率化をお考えなら、「クラウド在庫管理システムzaico」をご検討ください。
zaicoを利用することで、バーコードやQRコードスキャンで現物の入出庫や棚卸作業の効率化が可能になり、エクセルやCSVからデータを一括で登録できるので、手作業からのデータ移行も簡単に行えます。
現品管理や在庫管理の効率化やシステム導入をお考えであれば、お気軽にzaicoにお問い合わせください。