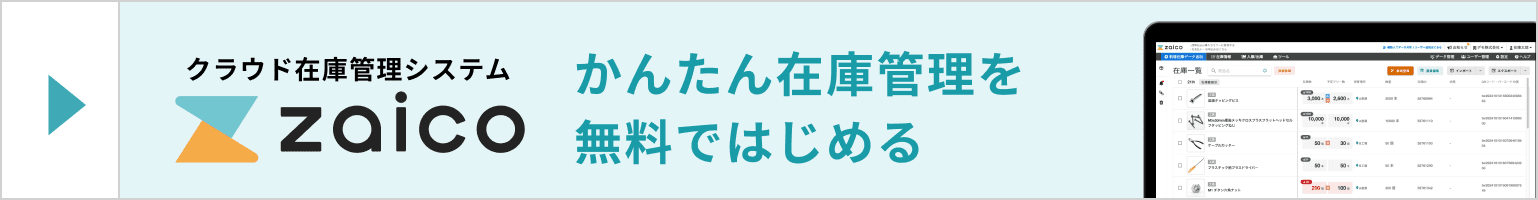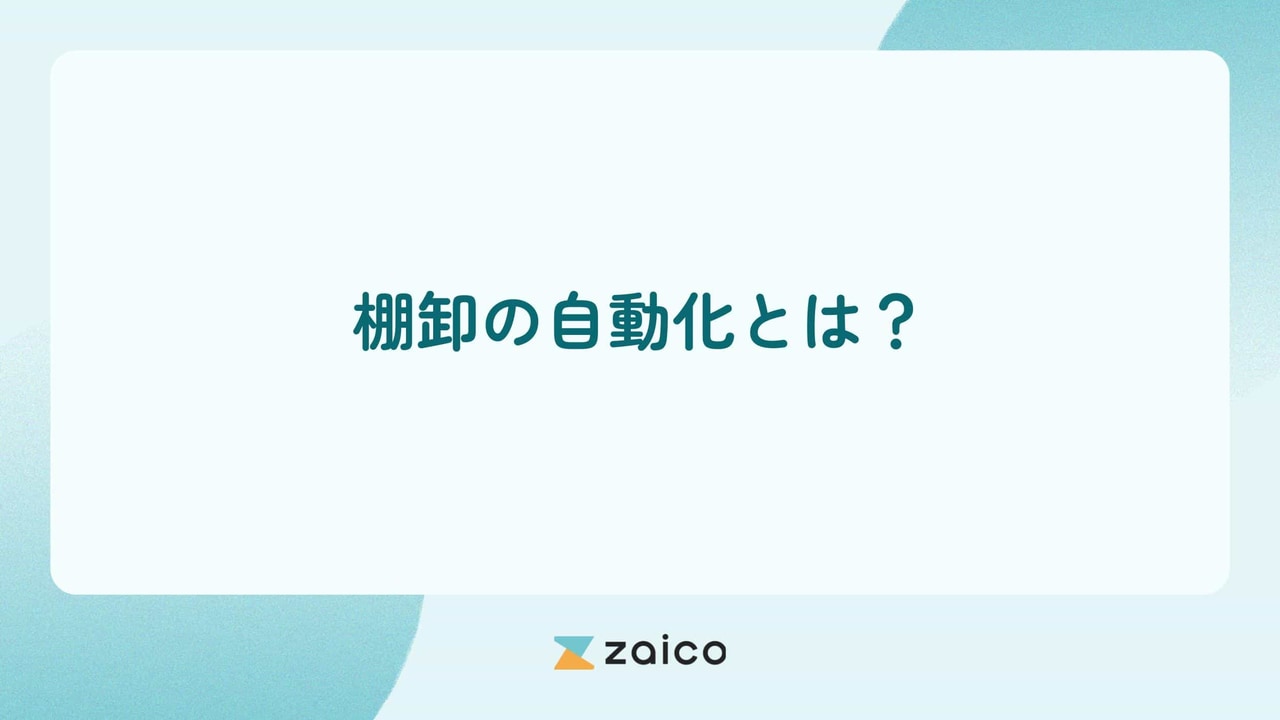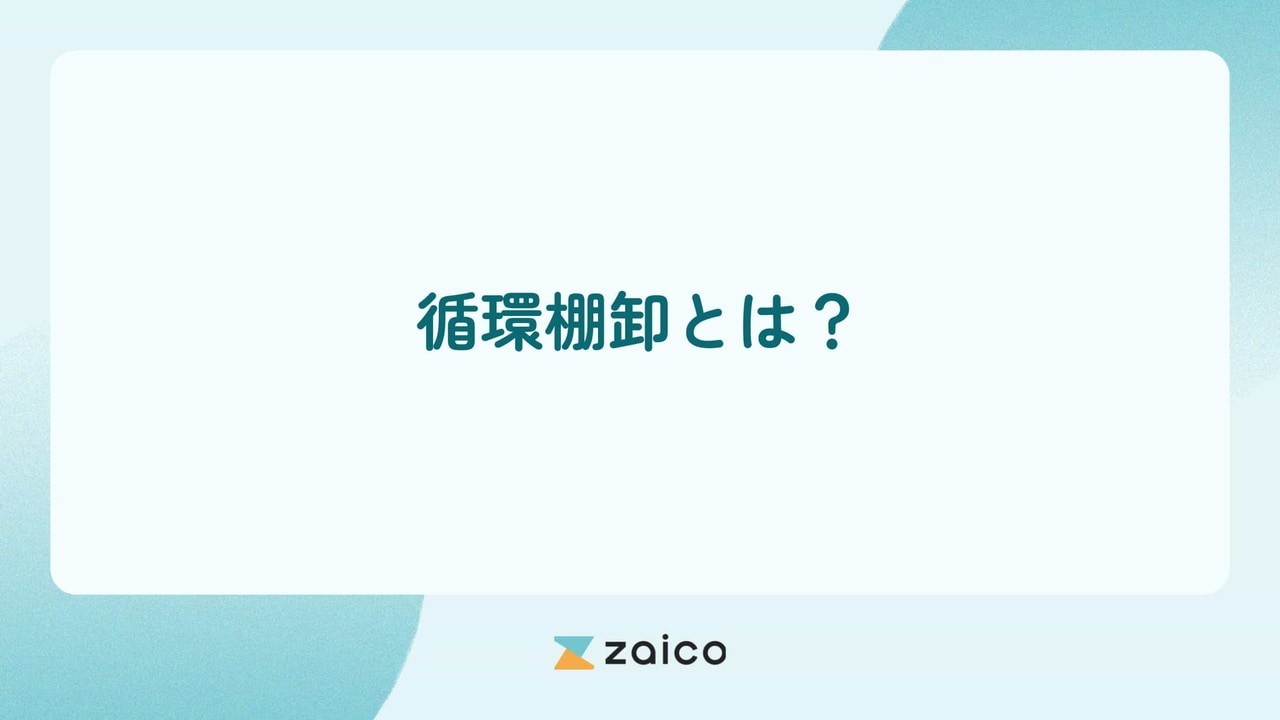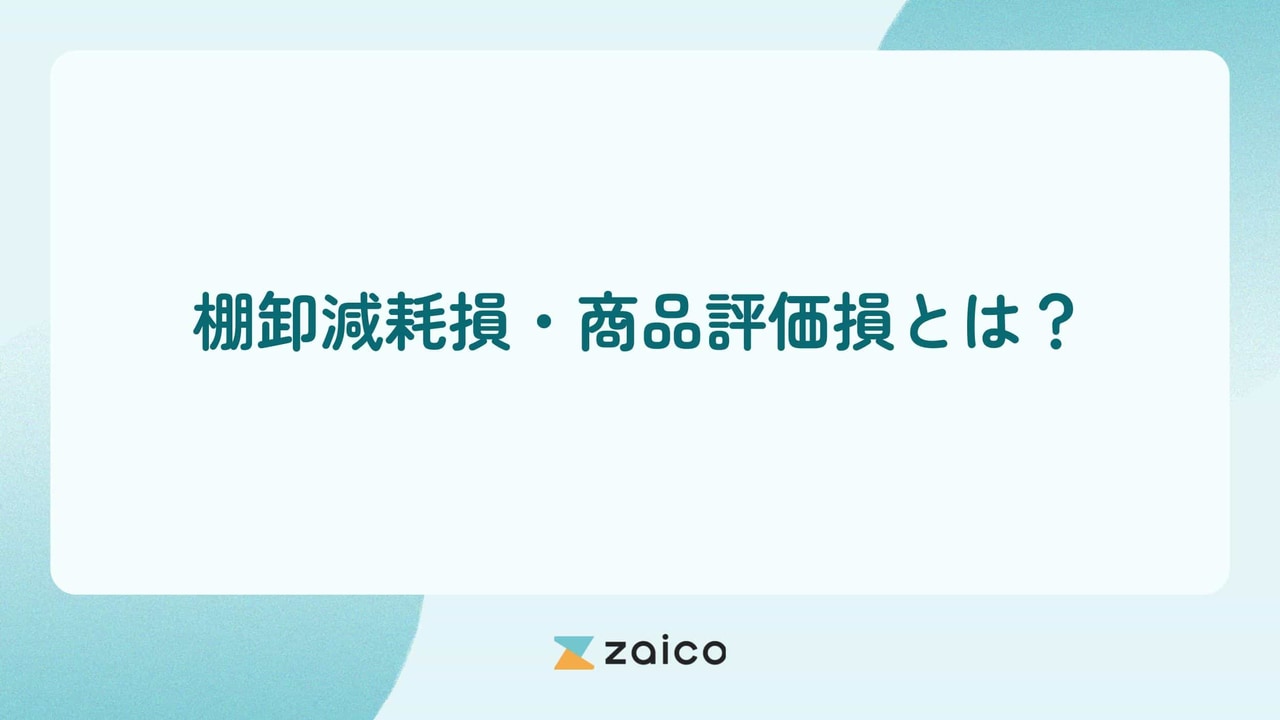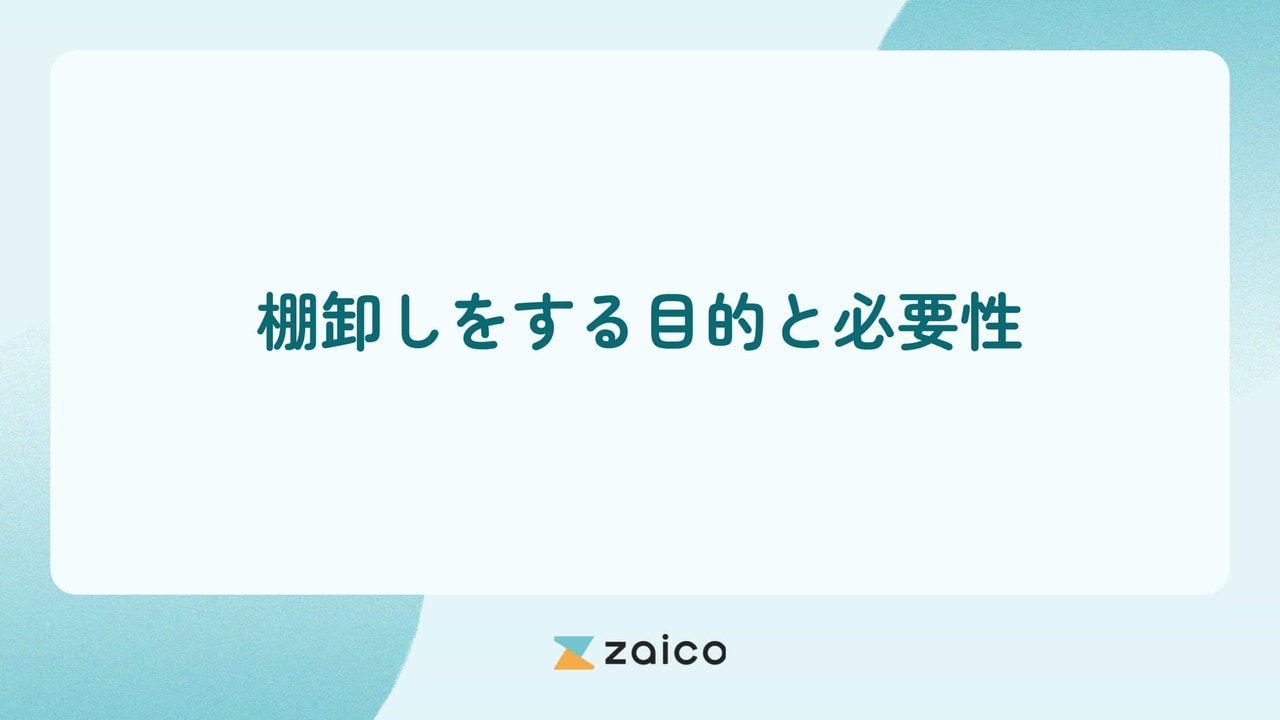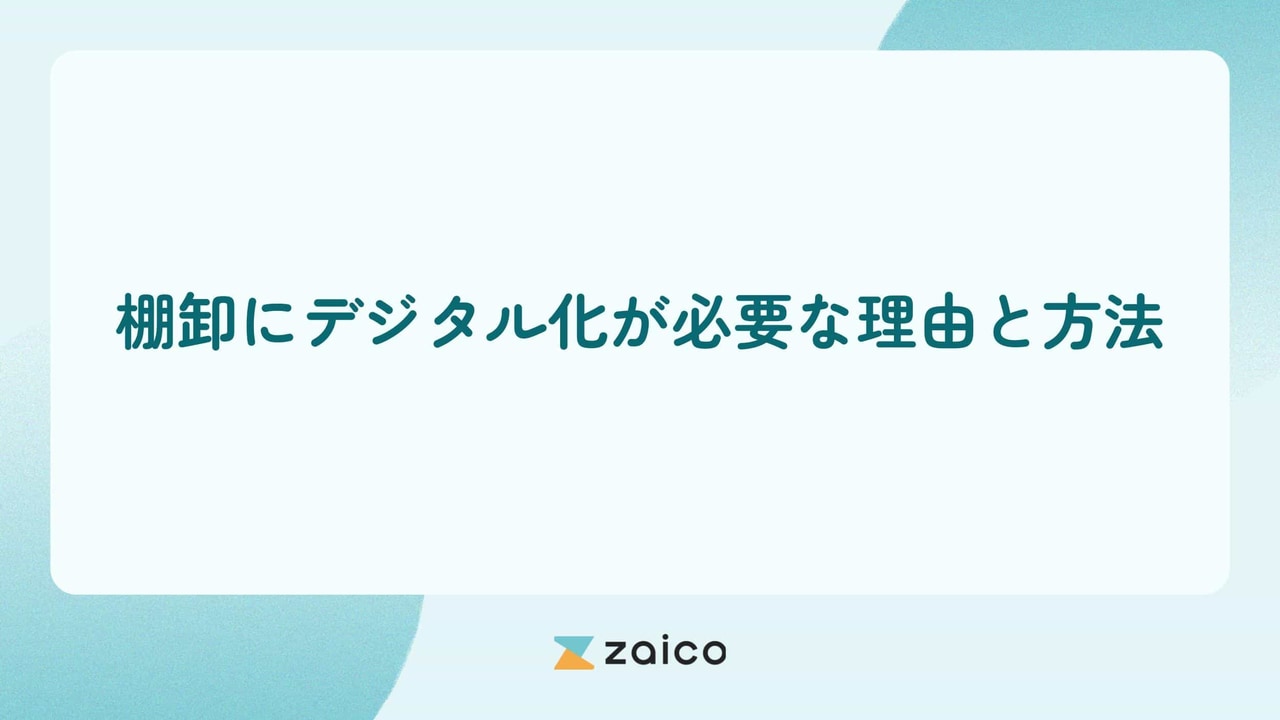棚卸は在庫管理の管理方法にミスがないか経費の計算は合っているかなどの、確認作業でもあり、隔週であったり、毎月行うところもあるでしょう。
棚卸をしているところは多くありますが、棚卸はいつやるのが良いかはそれぞれ違う場合があります。
棚卸はいつやるのが良いのか、棚卸をいつやるか決める際のポイントを確認していきましょう。
棚卸をいつやるかは重要?
棚卸は在庫管理の一環でもあり、主に以下の目的から行います。
- 在庫数が合っているかどうかの確認
- 経費の計算が正しいかどうかの確認
- 在庫管理表にミスがないかの確認
棚卸は、普段から行っている在庫管理が正しいかどうかを確認するために行うことが多く、頻繁に納品するものがある場合や在庫数が多い場合は定期的に棚卸を行う場合もあります。
在庫の入れ替わりや増減が多ければ多いほど、定期的に確認しないと棚卸作業自体に時間がかかってしまうからです。
また、棚卸をしなければ、在庫管理のミスに気付くのが遅くなり、無駄な作業が発生してしまう可能性も高まってしまいます。
そのため、棚卸をする場合はいつやるのかを決めるだけではなく、期間や頻度を決めることも大切です。
棚卸はいつやることが多い?
棚卸はいつやることが多いのでしょうか。
棚卸はいつやることが多いのかタイミングを確認していきましょう。
3月決算なら3月
3月に決算をする会社の場合、3月に棚卸作業を行うことが一般的です。
決算時期にはこれまでの売り上げや経費の計算を行うので、在庫管理の確認を行う必要があります。
もしも在庫数に違いがあれば見返す必要がありますし、経費の計算も変わってくるので決算に間に合いません。
そのため、3月が決算時期であれば3月に棚卸作業をして、正しい数値を出せるように動くことになるでしょう。
6月決算なら6月
3月決算のときと同じで、6月決算の際も決算時期に合わせて行います。
決算といえば、3月や12月などの年末や年度末がメインと考えられがちですが、6月を選択する場合もあります。
繁忙期以外に決算を行えば他の作業が滞りにくくなるので、棚卸作業に時間もかけやすくなります。
また、決算月によっては税金に違いもあるので、6月に行ったほうが税金が安い企業もあるかもしれません。
このように、決算月に合わせて月に違いはあれど決算時期に棚卸をするケースは多く、一般的といえるでしょう。
毎週や毎月行う
在庫数が多い場合などは、毎週や毎月棚卸を行った方が良いこともあります。
棚卸は基本的に在庫管理表に間違いがないか確認していく作業がメインです。
決まった曜日や隔週であったり、月の始めや終わりに行うことで、在庫管理の徹底ができますし、棚卸作業も順調に進められるでしょう。
棚卸しが毎年一回だけだと、確認作業が多くて時間がかかってしまいます。
一方、定期的に棚卸を行えば一回の作業時間を減らすことができるので、ミスの早期発見やコストの節約につながるでしょう。
年に数回行う
年に数回行うだけでも、棚卸作業は順調に進めることができます。
たとえば、偶数月にだけ行ったりなど、棚卸をする月だけを決めておけば、年に6回は棚卸作業が可能です。
決算月にだけ行う会社も多いかもしれませんが、棚卸は定期的に行ったほうが、ミスがあった場合などにスムーズに確認作業を行うことができます。
しかし、定期的に行えるほどリソースを割くことができない場合もあるでしょう。
そのような場合は、棚卸を行う月を決めて、年に数回行えるようにルールを作ってしまうこともおすすめです。
棚卸をいつやるか決める方法
棚卸をいつやるかはどうやって決めれば良いのでしょうか。
棚卸をいつやるか決める方法について確認していきましょう。
在庫数から考える
まずは在庫数がどれくらいあるのか、確認してみましょう。
取り扱うものや在庫数が多い場合、棚卸作業を年に一回だけに絞ってしまうとミスが発見されなかったり、作業に時間がかかってしまうので、棚卸作業は定期的に行ったほうが良いでしょう。
一方、在庫数が少ない場合は、年に一回の棚卸でも充分かもしれません。
定期的に行っても良いですが、そこまで作業することがないのであれば、半年に一回や年に一回にするなど問題が生じないペースでするという考えでしょう。
作業する人数から考える
作業する人数が少ない場合は、以下のように棚卸を行っても良いかもしれません。
- 年に一回だけ全員で行う
- 担当者を一人決めて毎月行う
しかし、在庫数が多ければ多いほど、一人あたりの負担は大きくなります。
そのため、全員で毎月行ったり全員で定期的に行う方法も良いでしょう。
また、作業する人数が多い場合は年に一回の棚卸でも充分です。
大人数で行えるのであれば棚卸作業は短時間で済むので、決算月にだけ棚卸を行う方法でも良いかもしれません。
在庫管理方法から考える
在庫管理の方法が細かい管理方法の場合は、定期的に行ったほうが良いです。
たとえば、薬剤などをグラム単位で管理している場合はミスも生じやすいので、定期的に行った方がミスを発見しやすくなります。
この場合、年に一回のタイミングでミスを発見しても、どのタイミングでミスを生じたのか原因を究明するのは難しいでしょう。
細かく管理しているものがある場合は、定期的な棚卸を意識してみてください。
一方、ざっくりとしたストック管理をしている場合は、定期的に行わなくてもそこまで棚卸作業は難しくありません。
このように、在庫管理方法が細かいのか、それともざっくりとした方針なのかによって、棚卸の回数や時期を考えてみるのもいいかもしれません。
棚卸の方法から考える
棚卸をいつやるのかは、棚卸の方法によって考えるのも良いです。
たとえば、在庫管理している備品の種類にわけて棚卸をやるのか、それともすべての在庫を一斉に棚卸するのかなど具体的な棚卸方法を考えてみましょう。
その棚卸方法によっては、定期的に棚卸をした方が良い場合もありますし、年に一回の棚卸で良い場合もあります。
また、デジタルツールを導入していれば棚卸作業は簡単な作業となるので、年に1回の決算月に行うことで間に合う場合もあるでしょう。
一方、アナログな方法で管理している場合は時間がかかるので、定期的に行った方が良いかもしれません。
このように、棚卸の方法についてまずは決めて、その方法に合わせていつ棚卸しをやるのか、頻度なども決めるようにしましょう。
棚卸をいつやるか決める際のポイント
棚卸をいつやるのか決める場合は、どのようなポイントがあるのでしょうか。
棚卸をいつやるかを決めるポイントについて確認していきましょう。
負担にならない程度かどうか
棚卸を定期的に行う場合は、負担にならない程度の頻度で行いましょう。
たとえば、作業する人数が少ないのに繁忙期の時期に棚卸を行う場合、どうしても棚卸作業が負担になってしまいます。
定期的に行っているのであれば、わざわざ繁忙期の時期に棚卸を行う必要はありません。
繁忙期を避けて年に数回行うように調整したりなど、作業する人が負担を感じにくい頻度で行うようにしましょう。
ツールを導入するかどうか
棚卸を行う場合は、アナログよりもデジタルで行ったほうがスムーズに進めやすく、ミスも発生しにくい傾向があります。
そのため、棚卸を効率化するツールを導入してみるのも良いでしょう。
ツールを導入してしまえば、日頃の在庫管理も簡略化できますし、定期的に行わなくても管理が煩雑になることはありません。
また、ミスがみつかりやすいというメリットもあるので、日頃の在庫管理のときからミスなく管理がしやすく、棚卸で在庫管理をやり直すという事態にも発展しないでしょう。
棚卸の作業効率からいつ行えば良いのか分からない場合は、ツールを導入して効率化してしまえば、いつやるのが最適なのか判断できるようになるかもしれません。
棚卸の影響はどれくらいか
棚卸は在庫数や資産の把握を目的で行うものでもあるので、これらの間違いがどれくらい影響するかどうかも考えなければいけません。
多少ずれていても運営や営業に問題ない場合は、あまり定期的にやらずにまとめてやってもいいかもしれませんが、影響が大きいようならミスを早期発見できるように定期的にやったほうがいいといえるでしょう。
また、棚卸をいつやるかという観点からも棚卸の影響度を踏まえて、毎週したほうがいい、毎月でいい、数カ月に一回でいい、年一回でいい、という風に考えてみるといいかもしれません。
棚卸をいつやるか決めたらzaicoで効率化
棚卸は作業する人数や在庫数、扱うものに合わせて、いつやるか、どのくらいやるのかを決めることが大切です。
棚卸をいつやるか決めた後は、デジタルツールを導入して棚卸作業を効率化しましょう。
棚卸作業を効率化したい場合は、「クラウド在庫管理システムzaico」の導入を検討してみてください。
zaicoはクラウドで管理できる在庫管理システムになり、在庫管理や棚卸のデジタル化にも役立ちます。
実際に、zaicoを利用して棚卸作業の効率化を実現した事例も多くあるので、棚卸をいつやるか決めて在庫管理システムの利用もお考えであれば、お気軽にzaicoにお問い合わせください。