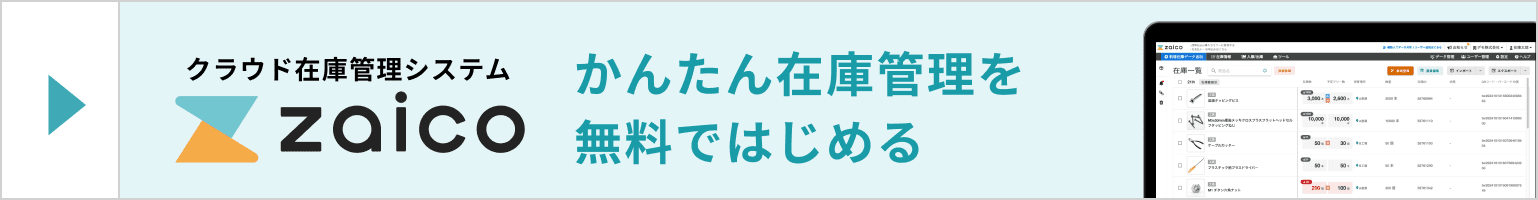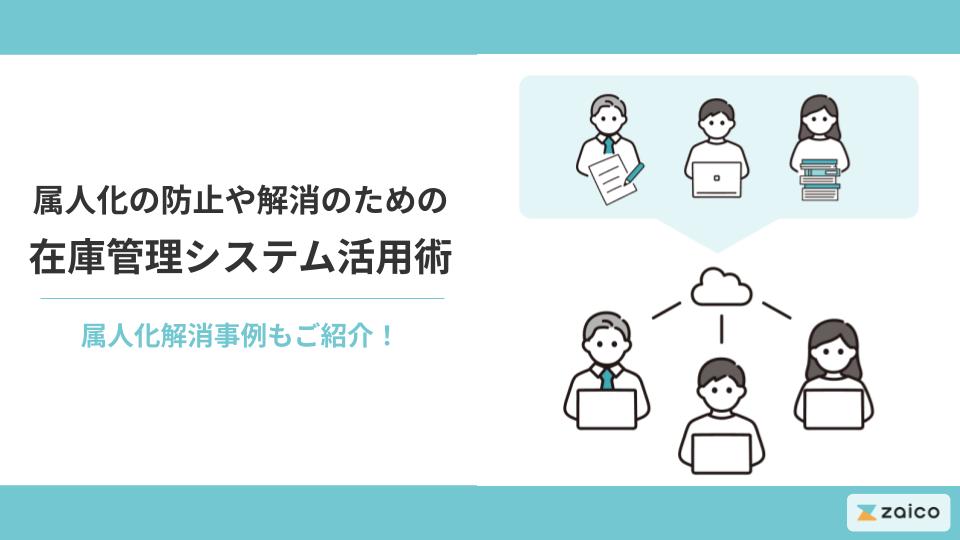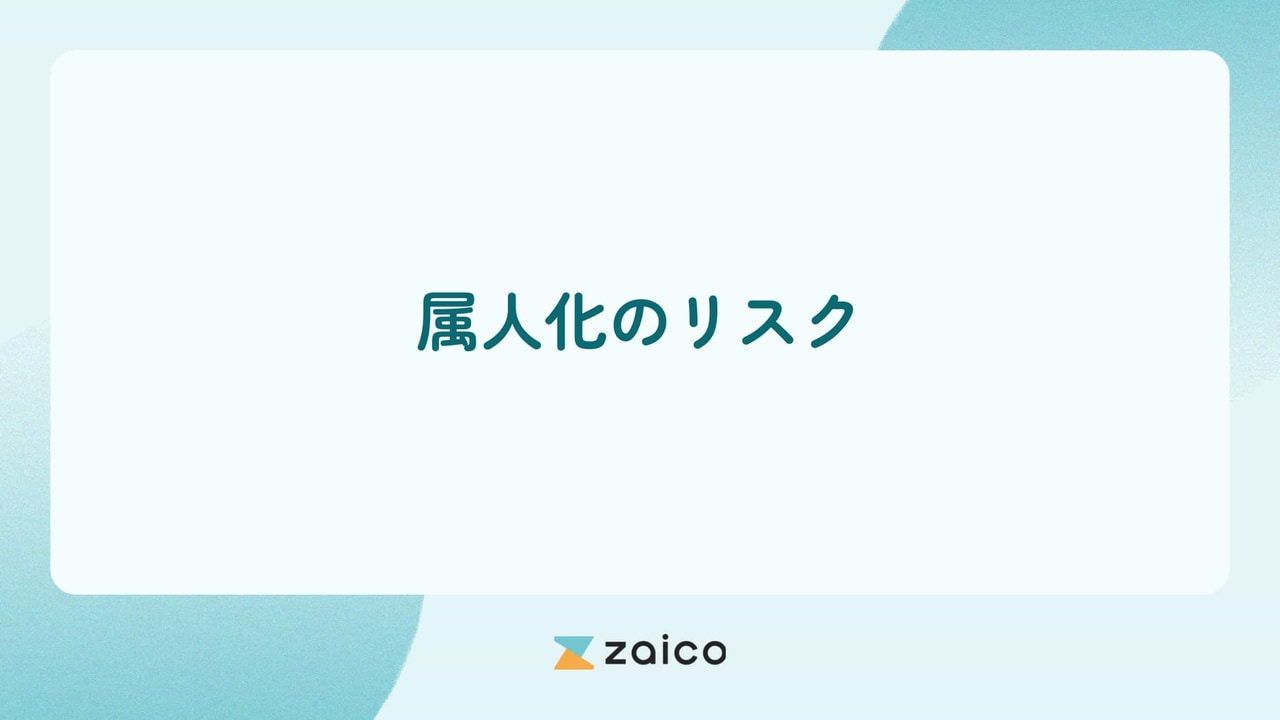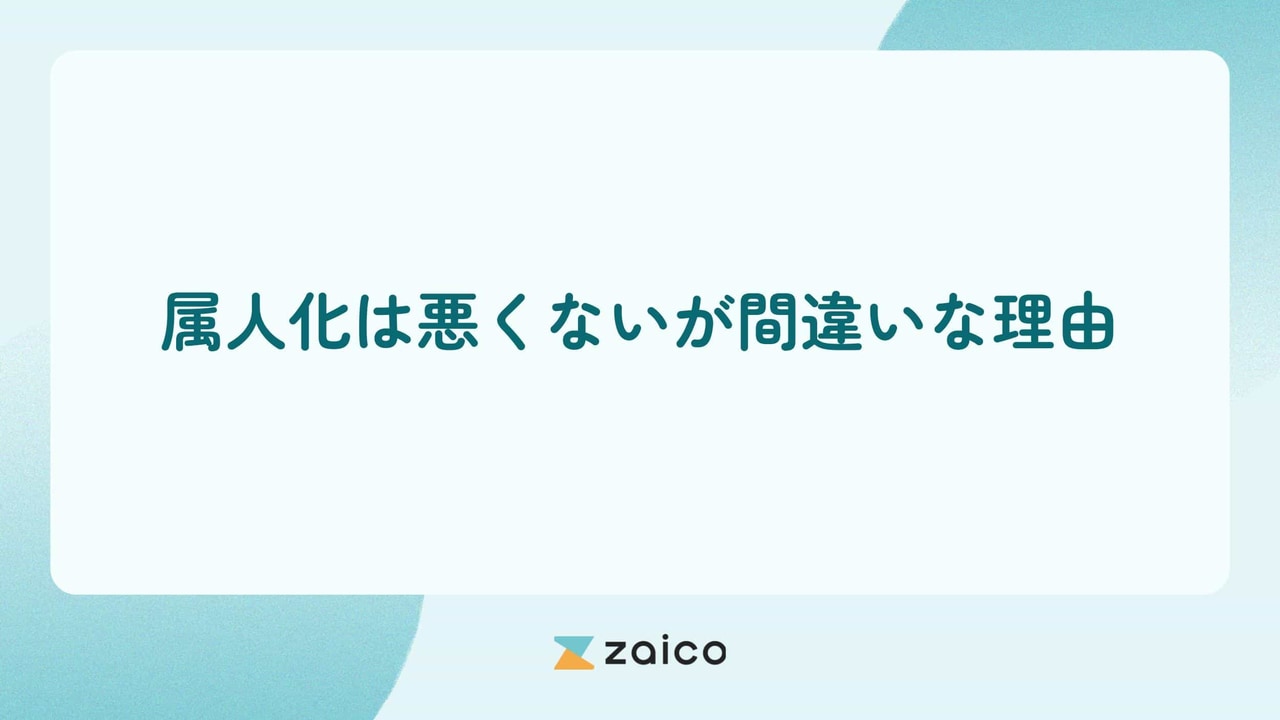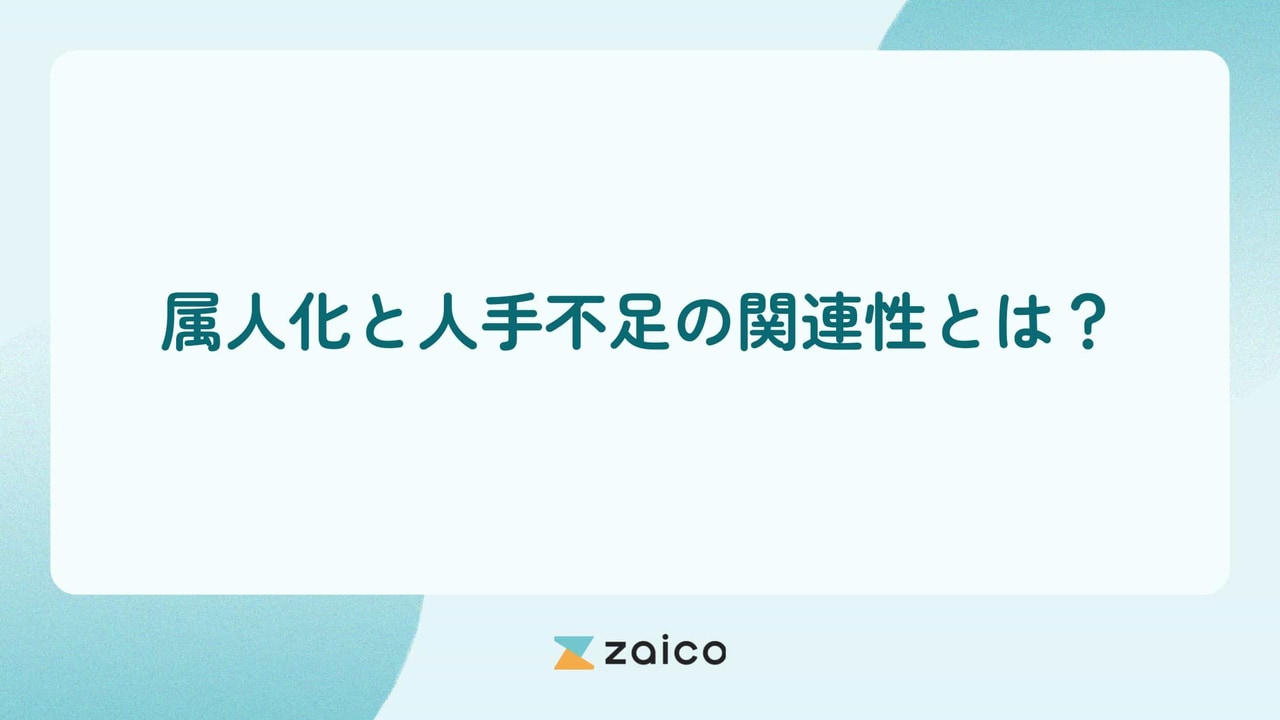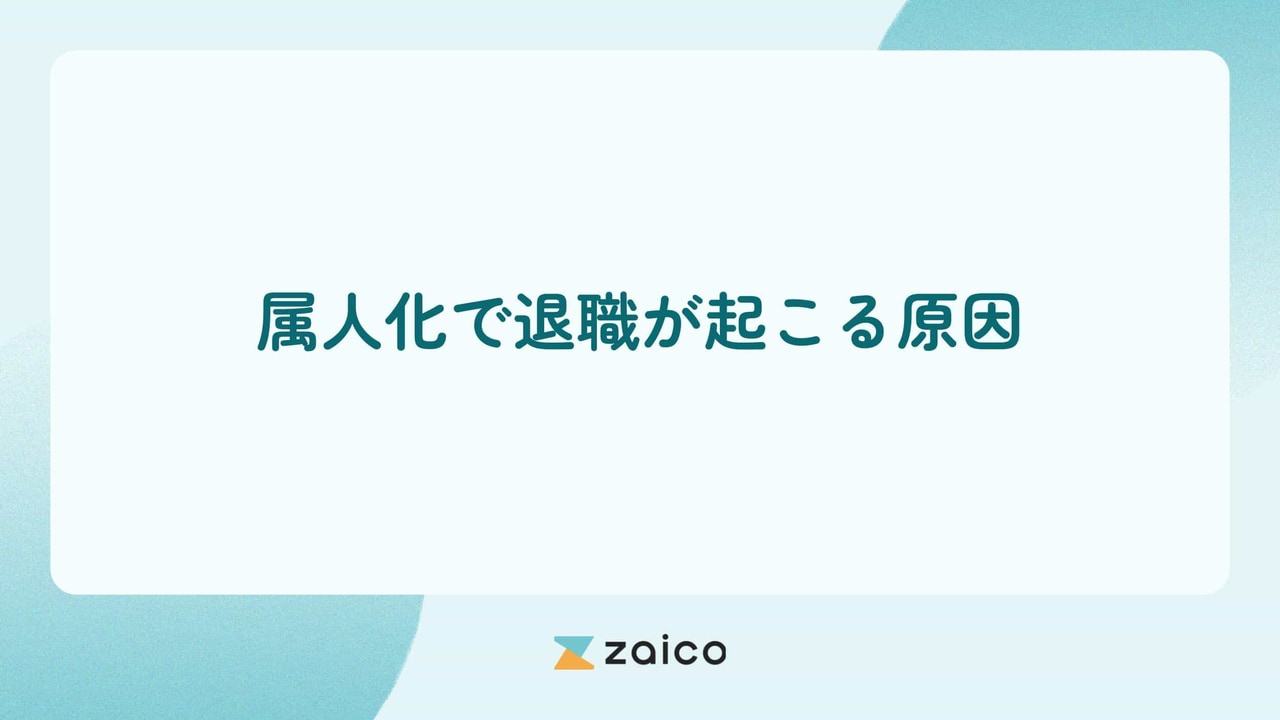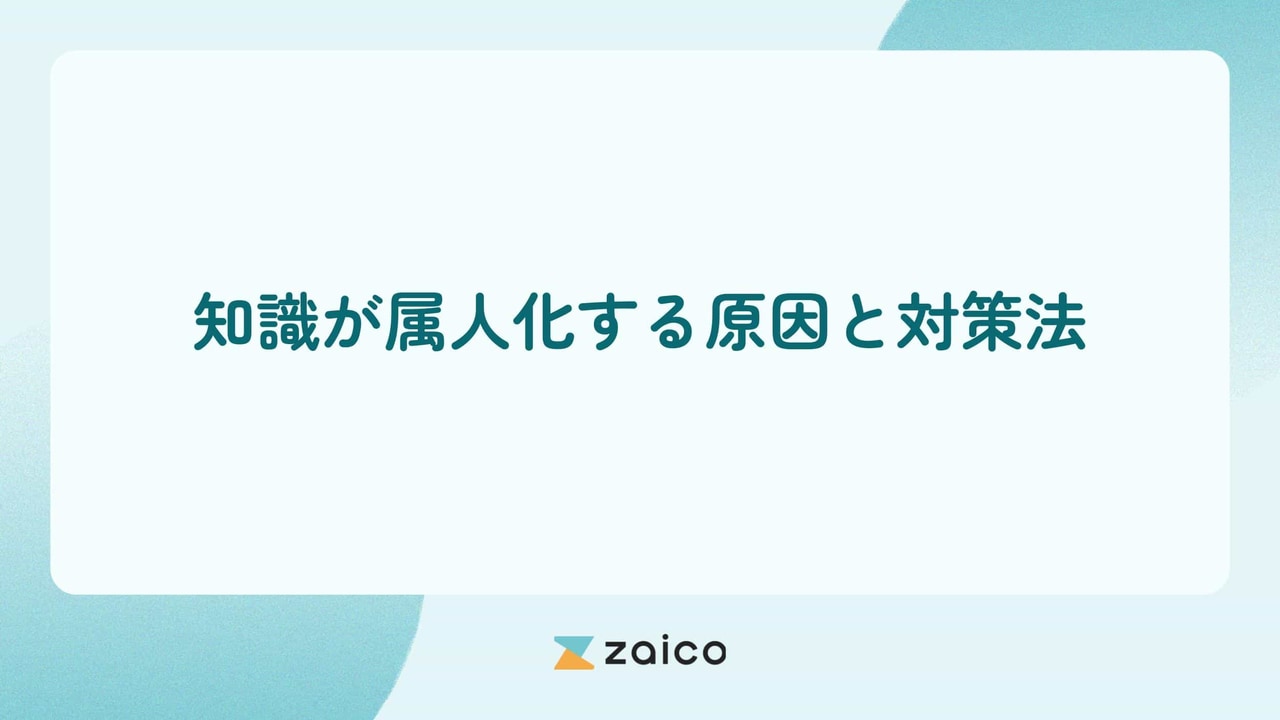特定の人しか業務できない状態になってしまう属人化は、企業としては避けたい状態です。
属人化が進むことで業務に影響が出たり、潜在的な問題を抱えてしまうだけでなく、属人化が退職理由になってしまうこともあります。
属人化が退職理由になってしまう具体的なケースを確認し、なぜ属人化が退職理由となってしまうのか、属人化が退職理由になりやすい組織の問題点、属人化を退職理由にさせないための解決策を考えていきましょう。
属人化が退職理由になるケースがある
そもそも属人化は、組織課題として第一想起されづらいことが多い傾向があります。
残業時間や給与などのように数で測ることができませんし、細かい作業ほど属人化されやすいこともあるため、属人化の課題以前に属人化自体が明るみに出づらいことがあります。
加えて、属人化した業務を引き受けている本人は優秀であることも多く、それが余計に周囲に属人化を気づかせないこともあるでしょう。
社内でノウハウがないことを初めて手がけたり、自己裁量で進められるだけの権限があったりする社員は、エースやベテランであることも少なくありません。
しかし、属人化された仕事を持った社員は、必要以上に頼られることや、自分がいないと業務が回らない環境に対するストレスを抱えてしまいます。
その結果として、属人化が理由で、活躍していた社員が急に退職してしまうことがあります。
属人化が退職理由になる原因
属人化が退職理由となる具体的な原因は何なのでしょうか。
属人化された業務を任されている本人だけでなく、属人化によって影響を受けている周囲の退職理由にもなってしまう可能性があります。
属人化が退職理由になる原因を確認していきましょう。
仕事が一部に集中することで不公平感から
属人化された業務を任されている人が、それに不公平感を感じることが、属人化が退職理由になる最もわかりやすい原因でしょう。
仕事が属人化している環境では、成果を出せたり、ノウハウがある人に仕事が集中しがちになります。
新しい仕事が舞い込んだ時は、「この人に任せておけば大丈夫」と実績のあるメンバーに割り振るでしょうし、専門的な知識が必要な時は、「何かあればこの人に聞けばいい」と、自分で学ばずに対象の社員に質問したり、依頼してしまうでしょう。
このように仕事が属人化された環境であれば、任される人は、同じ職位にもかかわらず、自分ばかり仕事が押し付けられるような不公平感を感じやすくなります。
また、属人化が当たり前になっている職場では、逆に仕事を任されない社員も生まれてしまいます。
そうした社員にとっては、成果をあげた社員ばかりが優遇され、自分にはチャンスが与えられないことに不満を抱えてしまうかもしれません。
この場合も、属人化によって仕事が一部集中することへの不満につながり、退職理由となってしまうこともあるでしょう。
ノウハウが共有されず成長できない
属人化によって専門知識や仕事のノウハウがブラックボックス化された結果、成長できないことに不満を感じ、退職に繋がってしまうこともあります。
個人の裁量が大きい環境では、例え同じ業務を抱えていても、進め方が個人に一任されていることは珍しくありません。
その際、上手くいった事例やノウハウなどが共有されていれば、社員が互いに高め合い成長できるのですが、属人化が当たり前な職場ですと、そうした共有がなされていないことが非常に多いです。
必要な情報が共有されなかったり、コミュニケーションがとりにくい状態であれば、新卒や中途入社した社員が、 ハイパフォーマーや先輩から学びを得る機会がなく、自力で良いやり方を見つけなくてはならなくなります。
非効率な仕事を繰り返した結果、成果が出ず、仕事のチャンスが余計にもらいづらくなってしまうという悪循環に陥ってしまい、退職してしまうケースがあります。
仕事の歩留まりが発生するストレスから
属人化が定着した結果、仕事の歩留まりが起き、そのストレスが退職理由になることがあります。
特定の仕事を「この人が詳しいから」といった理由で、ノウハウを持った人にのみ集約すると、その人ではないと対応できない仕事が生まれてしまいます。
そうした属人化された職場では、その人が休んだり、いなくなってしまうことで、仕事が止まってしまうことがあります。
一部の人の勤怠によって、チームやプロジェクト全体に歩留まりが発生してしまうことへのストレスは、退職理由になりうるかもしれません。
また、属人化した仕事を任されている本人としても、「自分がいないことで迷惑をかけてしまう」という心理から仕事が休みづらくなり、結果的により良い就業環境を求めて退職してしまう可能性もあります。
チームワークの悪さ・孤立感から
属人化された就業環境のムードの悪さが、退職理由に繋がってしまうことも珍しくありません。
属人化がデフォルトになっている環境は、チームワークを発揮しづらいという傾向があります。
属人化された職場は裁量を個人に任せていることが多いため、各社員が独自のやり方で仕事を進めています。
それぞれが我流で仕事をしているようなものなので、隣の人がどんな仕事をどんなやり方でしているかわからないという環境は、孤独を感じやすいでしょう。
また、せっかくのチームなのに協力しあう雰囲気がなかったり、例え協力したくても、そもそも相手が何をしているか知らない状況では、声をかけるのが憚られるかもしれません。
属人化の結果生まれたチームワークの悪さや、何かあっても助けてもらえなそうという不安や孤独感が退職理由になってしまうこともあるでしょう。
属人化が退職理由になる場合の問題点
属人化が退職理由になってしまっている企業や組織にはどんな問題点があるのでしょうか。
自社に当てはまることはないか、属人化が退職理由になる場合の問題点を確認していきましょう。
個人の裁量任せになっている
属人化が退職理由になることがある場合、仕事が個人の裁量任せになってしまっているかもしれません。
裁量を与えることは一概に悪いことではありませんし、裁量や権限を与えられることでやる気が出るタイプの人も多いです。
しかし、裁量を与えるだけ与えて放置してしまうと、仕事がブラックボックス化され、結果的に属人化を生んでしまうことがあります。
例えば、営業成績が優秀な若手メンバーをマネージャーに昇格させたとします。
その場合、チーム方針やメンバー育成の裁量を渡すことが一般的でしょう。
もしその人がいくら営業として優秀であったとしても、チームマネジメントや部下の育成が初めてなのであれば、任せっきりにせず、サポートは必要になるはずです。
裁量を与えて「あとはよろしく」といった環境では、社員は組織を頼ることができず、我流の仕事の進め方に頼らざるを得なくなってしまいます。
業務量が多すぎる
属人化が退職理由になっている仕事は、そもそもの一人当たりの業務量が多すぎることも珍しくありません。
業務量が増えているにもかかわらず、業務フローや業務割り振りが体系化されておらず、その場しのぎで担当者が判断し対応をしているような職場ほど属人化が見受けられます。
なぜなら、各担当者がそれぞれ異なる仕事の対応方法を確立し、結果それがルーティンになってしまうことで、属人化が生まれてしまうからです。
チームの中で定期的なノウハウ共有がされていれば、業務も効率化され洗練されていくでしょうが、業務量が多すぎる環境では、そうした共有に割く時間も取りづらいものです。
その結果、自分なりの仕事の裁き方は知っていても、非効率な方法でしか対応できず、さらなる業務の追加に余裕を持って対応できないという悪循環が生まれてしまいます。
任せている業務量は適切か、体制作りやノウハウ共有に割けるだけの時間的・精神的な余裕があるか見直してみましょう。
専門知識を習得する機会がない
専門的なスキルや新しい知識を学ぶ機会がない職場では、属人化を退職理由に挙げる人も出てくるでしょう。
属人化された環境においては、専門知識がある人に特定の業務が偏る傾向があります。
逆を言えば、専門知識がなければ、その業務に携わるチャンスがないということです。
企業や組織が、研修制度やノウハウ共有環境の構築を後回しにして、スキル習得を個々の社員の意欲頼りにしている場合、専門性のある業務を割り振れる社員を確実に増やすことはできません。
すでにスキルを持っている社員に頼り続ける構図があり、属人化によって社員間の不満が溜まりやすくなっていそうであれば、知識習得の機会を企業側から積極的に社員に提示するようにしましょう。
助け合いのカルチャーがない
企業風土として、互いに助け合う文化がない職場は、属人化を招きやすく、それが退職理由にもなりかねません。
例えば、社員同士をライバルとして競わせるような風土などは、やり方を間違えると、同僚を出し抜くために業務ノウハウを自分だけの秘密にしてしまうといった属人化を招いてしまうかもしれません。
チームで助け合うことのメリットがなく、「自分のことだけすればいい」という文化では、工夫の共有や悩みの相談などがされず、各社員が個人事業主のように仕事を進めてしまうでしょう。
何のためのチームなのか、社員同士でどんなシナジーを発揮して欲しいのかを明確にし、それに適した制度やムードの構築を進めていく必要があります。
属人化を退職理由にさせないための対策ポイント
属人化を理由とした退職者を出さないためにはどうすればいいのでしょうか。
属人化を解消し生ませない職場作りのためのポイントを確認していきましょう。
属人化しやすい業務や業務フローの可視化を行う
最初にすべき対策として、現在の業務フローや実際の業務の運用方法を洗い出し、可視化しましょう。
組織として想定している業務フローを全員が同じように行っているのかの確認から始め、各社員がどういったオリジナル要素のある業務を持っているのかを明確にしていきましょう。
また、主業務以外の細かい仕事ほど、意外と属人化が起きていることがあります。
例えば、利用頻度の低いソフトウェアを使った業務や、特例で昔からの体制のまま続いている業務などです。
細かい箇所まで業務内容を確認すると同時に、「それは他の人でも対応が可能な仕事か」をチェックしていきましょう。
業務・権限の適切な采配をする
業務や権限が一部に集中していると、属人化は起きやすいものです。
その人がいないと業務が回らないという状況を避けるためにも、業務割り振りや権限の采配状況を見直しましょう。
その際、「最も良い成果を生む」ためのベストな采配をしようとするのではなく、「一定のクオリティを保つ」ことを目標とした采配を意識しましょう。
そうしないと、必要以上に基準が高くなり、属人化に繋がりやすくなります。
期待する品質が保てるレベルであれば、積極的に業務や権限の割り振りを行いましょう。
また、決裁権限を分け、関係者が共通のワークフローやフォーマットを使う環境を整備することも、属人化を防ぐのに繋がるため効果的です。
知識・ノウハウ共有体制と教育制度を充実させる
属人化を退職理由にしないためには、業務知識やノウハウを常に共有できる仕組み作りや、幅広い人が受けられる教育制度を充実させることがポイントです。
知識やノウハウが共有されていれば、イレギュラーな業務が発生した時に対応できる社員が増えるため、特定の社員に負担が偏るリスクを減らせます。
新しい知識を得ることで任される業務の幅も増えるため、社員が成長を実感しやすくもなるでしょう。
また、教育制度の整備に関しては、制度を作る過程で仕事のやり方を言語化する必要があるため、属人化に頼らない職場作りにも繋がっていくでしょう。
属人化を防ぐITツールの導入を進める
属人化を退職理由にさせないためには、情報共有などのITツールを導入するのも効果的です。
属人化は、個人が仕事をブラックボックス化してしまうことで起きます。
ITツールを活用して、仕事内容がいつでも、誰にでもわかる状況を作ることができれば、属人化のリスクを大きく下げることができるでしょう。
例えば、業務フローの各状況を可視化するツールを導入して、業務量が集中している箇所にすぐにヘルプに入れるようにしたり、事例やノウハウをデータベース化できるツールを使って、困った時に誰かに聞かずとも自力で解決できることを増やしたりするなど、属人化をITツールで解消する方法はたくさんあります。
自社の属人化の課題がどこにありそうか見通しが立ったら、解決に繋がるITツールを検討してみましょう。
属人化を退職理由にしないためにもzaico
属人化を退職理由にしないためには、業務状況を洗い出し、属人化が起きている・起きやすい箇所を明確にした上で、適切な解決策をとっていきましょう。
もし、在庫管理業務がある企業であれば、「クラウド在庫管理システムzaico」は属人化の解消に大きく貢献できるかもしれません。
17万社以上への導入実績があり、継続率も90%以上と、多くの企業に使われている「zaico」は、面倒な在庫管理業務をスマホ・PCで簡単に行うことができます。
在庫状況をスマホアプリでリアルタイムに更新・確認ができ、現在庫、入庫・出庫予定、履歴などのデータを誰でもいつでも確認することができるので、属人化で起きがちな業務のブラックボックス化や、一部の社員への業務負担の偏りを防ぐことができます。
また、欠品が出そうな時は自動的にアラートが立つなど、属人的にならない仕組み化も「zaico」の機能で簡単に行えるため、在庫管理において属人化で退職者を出さないための職場作りに役立つでしょう。
属人化が退職理由となる退職者を出さないための職場作りや在庫管理の属人化の解消をお考えであれば、お気軽にzaicoにご相談ください。